


② 前書き(この記事でわかること)

とびひは、子どもにとても多い皮膚の細菌感染症です。正式な病名は
「伝染性膿痂疹(でんせんせいのうかしん)」といいます。火事の火の粉のように、あっという間に広がることから「とびひ」と呼ばれています。
この記事では、薬局薬剤師の視点をまじえながら、次のようなポイントを丁寧に解説していきます。
- とびひ(伝染性膿痂疹)の原因・症状・種類
- 病院で行われる治療(塗り薬・飲み薬)の考え方
- お風呂・プール・登園・登校の目安
- 兄弟や家族にうつさないための工夫
- 薬局でよく聞かれる質問と、その考え方
なお、この記事は一般的な医療情報であり、特定の方の診断・治療方針を決めるものではありません。実際の体調や皮膚の状態については、必ず医師・薬剤師などの医療専門職にご相談ください。

③ 本文
1. とびひ(伝染性膿痂疹)ってどんな病気?

1-1. 原因となる菌
とびひは細菌による表面の皮膚の感染症です。主な原因菌は次の2つです。
- 黄色ブドウ球菌
- 溶血性レンサ球菌(溶連菌)
これらの菌は、もともと皮膚や鼻の穴の入り口などに「常在菌」として住んでいることも多く、
皮膚に傷やかき壊しがあると、そこから侵入して増殖し、とびひを起こします。
きっかけとして多いのは…
- あせもをかきむしる
- 虫刺されをかき壊す
- 転んだ傷の処置が不十分
- アトピー性皮膚炎などで、皮膚バリアが弱くなっている
1-2. どんな見た目になる?(代表的な症状)
とびひの典型的な症状は次のようなものです。
- かゆみを伴う赤いブツブツ・水ぶくれができる
- 水ぶくれがやぶれてジュクジュクし、黄色〜茶色のかさぶたになる
- 指で触ったところに「うつって」別の場所にも同じような発疹が広がる
- 顔(特に鼻の周り)、手足、体などに多い
とびひは基本的に皮膚の表面だけの浅い感染ですが、放置すると広範囲に広がったり、まれに深い感染症につながることもあるため、早めに対応することが大切です。
1-3. 2つのタイプ(水疱性と痂皮性)
日本皮膚科学会のQ&Aでは、とびひは大きく次の2種類に分けられると説明されています。
| タイプ | 特徴 | よくみられる年齢・季節 |
|---|---|---|
| 水疱性膿痂疹(すいほうせいのうかしん) | 水ぶくれ(水疱)ができて、やぶれてびらん(皮膚がペロっとむけた状態)になる。 | 乳幼児〜小児に多い。特に夏場の高温多湿の時期。 |
| 痂皮性膿痂疹(かひせいのうかしん) | 炎症が強く、厚いかさぶた(痂皮)がつく。ジュクジュクよりも「かさぶた」が目立つ。 | 季節は問わず。子どもだけでなく大人にも見られる。 |

1-4. どれくらい「うつりやすい」の?
とびひはとても感染力の強い病気です。世界的に見ると、子どもの12%前後が経験する、かなり身近な感染症とされています。
感染の広がり方は主に次の通りです。
- 患部をかいた手で別の場所を触る → 自分の体の中で広がる
- 患部に触れた手でおもちゃ・タオルなどをさわる → それを通じて他の子どもにうつる
- 肌と肌が直接ふれあう遊び・格闘技・プールなどでうつる
そのため、「かゆくてかわいそうだから」といって放置すると、あっという間に全身に広がることもあります。早めに受診し、適切な薬とスキンケアを始めることが重要です。
2. 診断と受診の目安

2-1. 病院ではどうやって診断する?
とびひは、多くの場合皮膚の見た目(視診)と経過から診断されます。典型的な水ぶくれ・かさぶたの形、広がり方、かいた跡などが参考になります。
必要に応じて…
- 皮膚の表面をぬぐって培養検査(どの菌がいるか)
- 他の皮膚病との見分け(みずぼうそう、帯状疱疹、虫刺され、アトピー性皮膚炎の悪化 など)
が行われることもありますが、日常診療では視診だけで診断されることも多いです。
2-2. 受診した方がよいサイン
次のような場合は、自己判断で市販薬だけで様子を見るのではなく、早めに小児科・皮膚科を受診しましょう。
- 顔(特に目のまわり)に広い範囲でジュクジュク・かさぶたがある
- 発熱・ぐったり感・食欲低下など、全身症状を伴う
- 腕や脚に沿って赤い線が伸びる(リンパ管炎の可能性)
- 短期間で急速に広がっている
- 痛みがとても強い
- 赤ちゃん(乳児)や、持病で免疫が落ちている方
- 糖尿病など、傷が治りにくい基礎疾患がある
また、学校・保育園で「とびひが流行している」と言われた時も、軽症のうちに相談しておくと安心です。
3. とびひの治療:塗り薬と飲み薬

3-1. 基本は「抗菌薬の外用」
症状が限られた範囲で、全身症状がない場合は、抗菌薬の塗り薬(外用薬)が第一選択になることが多いです。
抗菌薬の外用薬は、原因菌(黄色ブドウ球菌や溶連菌)に効く成分が含まれており、
- 1日数回、患部とその周囲に薄く塗る
- ガーゼなどで覆って、他の部位や他人に触れないようにする
といった使い方をします。
日本では、ムピロシンなどを含む外用抗菌薬が使用されることがありますが、具体的な薬の選択や用量は医師が症状・年齢・既往歴を見て判断します。
3-2. 飲み薬(内服抗菌薬)が使われるケース
次のような場合には、飲み薬(内服抗菌薬)が併用・選択されることがあります。
- 病変が広範囲にある
- 発熱や全身のだるさを伴う
- リンパ節の腫れ・痛みがある
- 深い感染症を疑う所見がある
- 家庭の事情などで、こまめに塗り薬を塗ることが難しい
内服抗菌薬は、原因菌の種類や地域の耐性菌の状況なども考慮した上で選ばれます。処方されたら、自己判断で途中中止せず、決められた日数きちんと飲みきることがとても大切です。
3-3. ステロイド外用薬との関係
アトピー性皮膚炎の上にとびひが重なる「とびひ+アトピー」のようなケースでは、
- 炎症・かゆみを抑えるためのステロイド外用薬
- 細菌を抑えるための抗菌外用薬
を併用することがあります。
ただし、「赤いからとりあえずステロイドだけ塗る」「市販のステロイドで自己判断する」ことは避けるべきです。感染が強い状態でステロイドのみを使うと、かえって悪化することもあり得るためです。

市販薬や、以前もらった薬を自己判断で使う前に、一度医師・薬剤師に相談するようお伝えすると安全です。
4. お家でできるケア・生活上の注意点
4-1. 清潔を保つ:お風呂・シャワー
日本小児皮膚科学会のQ&Aでは、とびひの時でも入浴は基本的にOKとされています。ただし、次のようなポイントに注意します。
- 湯船よりもシャワーが望ましい
- 石けんをよく泡立てて、こすらず「手でなでる」程度に洗う
- 患部を洗ったタオルを家族で共用しない
- 兄弟がいる場合は、兄弟が先に入り、最後にとびひのお子さんが入る
- 入浴後は、医師の指示通りに軟膏を塗ってガーゼなどで覆う
4-2. かきむしり対策
とびひが広がる最大の原因は「かきむしり」です。かゆみを抑えること=感染を広げないことにつながります。
- 爪を短く切る
- 寝るときは手袋やミトンを使うことも検討
- 汗をかいたらシャワーで流し、こまめに着替える
- 医師から抗ヒスタミン薬が処方されている場合は、指示通りに使用
4-3. タオル・衣類・寝具
タオルやシーツには菌がつきやすいため、
「共有しない」「こまめに洗濯する」ことが大切です。
- タオルは「家族で1人1枚」を徹底
- 患部に当てたガーゼや包帯は、指定された方法で処分
- シーツやパジャマは、汗や浸出液で汚れたら早めに交換
5. 保育園・学校・プールはどうする?

5-1. 学校感染症としての扱い
伝染性膿痂疹(とびひ)は、学校保健安全法で「学校感染症」に分類されています。
日本小児皮膚科学会の解説では、次のようにまとめられています。
- 病変部をガーゼや包帯できちんと覆い、露出しなければ、通常は登園・登校を控える必要はない
- ただし、広範囲の場合や、重症な合併症(ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群など)がある場合は、休ませた方がよい
つまり、「きちんと治療して、患部を覆っていれば、必ずしも欠席しなければいけないわけではない」という考え方です。ただし、実際の運用は園や学校ごとに異なることがあるため、かかりつけ医の意見書や指示に従うことが重要です。
5-2. プールは基本的にNG
プールは、
- 肌と肌が直接ふれやすい
- 患部が水でふやけて広がりやすい
といった理由から、とびひが完全に治るまで原則として禁止とされています。
「かさぶたが残っているけど、もう菌は少ないから大丈夫でしょ?」と考えがちですが、見た目が落ち着いていても、まだ菌が残っている可能性があるため、医師と相談しながら再開のタイミングを決めましょう。
④ 症例・具体例・実践的なイメージ

ケース1:虫刺されをかき壊して広がった3歳児
・3歳の男の子。
・最初は足首の虫刺されをかきこわして赤くなった。
・数日で、足〜膝〜お腹にかけて、小さな水ぶくれと黄色いかさぶたが増えてきた。
・かゆみが強く、夜も眠りが浅い。
このようなケースでは、
- 小児科・皮膚科を速やかに受診
- 抗菌薬の外用+かゆみを抑える薬(抗ヒスタミン薬)
- 入浴はシャワー中心にし、患部をこすらない
- タオルは家族と分ける・爪を短くする
といった対応が一般的に行われることが多いです。
薬局では、塗り薬の塗る順序(保湿剤・ステロイド・抗菌薬など)や、入浴タイミングとの組み合わせを丁寧に説明すると、保護者の安心感につながります。
ケース2:アトピー性皮膚炎の悪化に重なった小学生
・小学校低学年の女の子。アトピー性皮膚炎で通院中。
・夏休み前後から汗でかゆみが悪化し、腕や脚をかきむしっていた。
・その上に水ぶくれ〜かさぶたが増え、「前よりジュクジュクしてきた」と受診。
この場合、
- アトピー性皮膚炎の炎症を抑えるステロイド外用薬
- とびひ部分には抗菌外用薬(必要に応じて内服抗菌薬)
- 汗対策・保湿などのスキンケア指導
など、「もともとの皮膚病」と「二次感染」の両方を考えた治療が必要になります。
薬剤師としては、
- どの範囲にどの薬を塗るのか(塗り分け)
- ステロイド外用薬の強さと使用期間
- 保湿剤の使い方(回数・量)
を図やメモを使って視覚的に説明すると、とても喜ばれます。
ケース3:家族内でとびひが「リレー」した兄弟
・保育園児の兄がとびひと診断され、治療開始。
・数日後、同居している弟にも同様の皮疹が出現。
・タオルやおもちゃを共有しており、寝るときも同じ布団。
このような家族内感染では、
- きょうだい全員の皮膚状態を一度診てもらう
- タオル・ハンカチ・パジャマなどの共有を避ける
- こまめな手洗いと爪切り
- おもちゃの定期的な拭き取り・洗浄
といった「環境全体」を見直すことが再発予防につながります。
薬局としても、処方された本人だけでなく、兄弟や家族の皮膚状態を一緒に聞き取ることで、より実践的なアドバイスができます。
⑤ まとめ

- とびひは正式には伝染性膿痂疹といい、黄色ブドウ球菌・溶連菌などによる皮膚の浅い感染症。
- 水疱性膿痂疹(みずぶくれ)と痂皮性膿痂疹(厚いかさぶた)の2タイプがある。
- かゆみが強く、かきむしったり、触った手を通して別の場所や他人に「飛び火」する。
- 治療の基本は抗菌薬の塗り薬で、広範囲・重症・全身症状がある場合は飲み薬も併用される。
- 入浴はシャワー中心なら多くは可能だが、プールは治るまで中止が原則。
- 学校・保育園は、治療を行い、患部を覆えば通常は出席可能とされるが、実際の判断は主治医と園・学校のルールに従う。
- 再発予防のために、爪切り・手洗い・汗対策・タオルの共用を避けるなど、日常生活の工夫が重要。

⑥ よくある質問(Q&A)
Q1. とびひは自然に治りますか? 病院に行かなくても大丈夫?
軽いケースでは自然に軽くなっていくこともありますが、放置すると広がってしまうリスクがあります。特に子どもでは、かきむしりやすく、家族内感染もしやすいため、医療機関での診断と適切な治療を受けることがすすめられます。
Q2. かさぶたになったら、もううつりませんか?
かさぶたがついてくると回復に向かっているサインではありますが、見た目が落ち着いていても、まだ菌が残っていることがあります。とくにプールや、肌がふれあう遊びでは感染のリスクがありますので、医師と相談しながら「いつまで注意が必要か」を確認しましょう。
Q3. とびひのときに、ステロイドの塗り薬を使ってもいいですか?
とびひ単独の場合、自己判断でステロイドだけを塗るのはおすすめできません。感染が強い部分にステロイドだけを使うと、菌が増えやすくなる可能性があるためです。
アトピー性皮膚炎など、もともとの炎症と重なっている場合は、医師の指示のもと、ステロイドと抗菌薬を上手に組み合わせることがありますので、必ず処方医に確認しましょう。
Q4. 兄弟にうつらないようにする、一番のポイントは?
一番大事なのは「かきむしりを減らすこと」と「タオル・寝具などの共用を避けること」です。
- 爪を短く切る
- 抗ヒスタミン薬や保冷材などで、かゆみを上手にコントロール
- タオル・ハンカチは家族で1人1枚
- お風呂は兄弟が先、とびひの子は最後に入る
これだけでも、感染の広がりはかなり違ってきます。
Q5. 抗菌薬はどれくらいの期間使えばいいですか?
外用・内服ともに、医師が指定した日数・回数を守ることが基本です。自己判断で早く中止すると、菌が残って再燃したり、耐性菌の問題につながることがあります。
一方で、「良くなったのに漫然と塗り続ける」のも望ましくありません。気になるときは、自己判断せず、必ず医師・薬剤師に相談しましょう。
⑦ 参考文献
- 公益社団法人 日本皮膚科学会 皮膚科Q&A「とびひ」
https://qa.dermatol.or.jp/qa13/index.html
最終確認日:2025年11月25日 - 公益社団法人 日本皮膚科学会 皮膚科Q&A「とびひ Q1」
https://qa.dermatol.or.jp/qa13/q01.html
最終確認日:2025年11月25日 - 公益社団法人 日本皮膚科学会 皮膚科Q&A「とびひ Q2」
https://qa.dermatol.or.jp/qa13/q02.html
最終確認日:2025年11月25日 - 日本小児皮膚科学会 Q&A「とびひ」
https://jspd.umin.jp/qa/02_tobihi.html
最終確認日:2025年11月25日 - PACE とびひ(伝染性膿痂疹)とは?子どもと大人の症状の違いや原因
https://www.ns-pace.com/article/category/feature/impetigo/
最終確認日:2025年11月25日 - Koning S, et al. Interventions for impetigo. Cochrane Database Syst Rev.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7025440/
最終確認日:2025年11月25日 - Barbieri E, et al. Non-bullous Impetigo: Incidence, Prevalence, and Management in Children. Front Pediatr. 2022.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2022.753694/full
最終確認日:2025年11月25日 - Medscape. Impetigo Treatment & Management.
https://emedicine.medscape.com/article/965254-treatment
最終確認日:2025年11月25日 - 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)
「バクトロバン鼻腔用軟膏2% くすり情報 一般の方向け」
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/rdDetail/iyaku/6119700M1035_1?user=2
最終確認日:2025年11月25日
📘『薬局長のためのモンスター社員対応マニュアル』発売のお知らせ
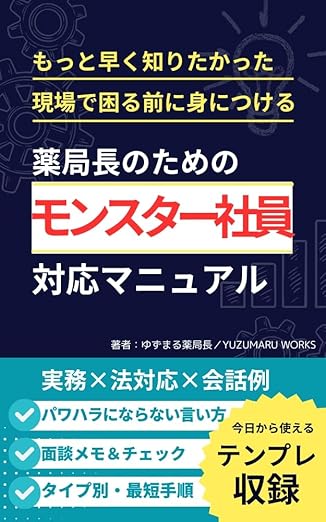
薬局で働いていると、どうしても避けられないのが「人間関係のストレス」。
患者対応、スタッフ教育、シフト調整……。
気がつけば、薬局長がいちばん疲れてしまっている。
そんな現場のリアルな悩みに向き合うために、管理薬剤師としての経験をもとにまとめたのが、この一冊です。






『薬局長のためのモンスター社員対応マニュアル』
― 現場で困る前に身につける 実務 × 法対応 × 会話例 ―
薬局で起こりやすい“モンスター社員”を15タイプに分類し、
それぞれの特徴・対応法・指導会話例を紹介。
パワハラにならない注意方法や、円満退職・法的リスク回避の実務ステップも具体的に解説しています。
- 現場によくある「人のトラブル」15パターンと対応のコツ
- パワハラにならない“安全な指導”の伝え方
- 円満退職を導くための面談・記録・法的ポイント
- 薬局長自身を守るマネジメント思考
薬局で人に悩まないための「実践マニュアル」として、
日々の業務の支えになれば幸いです。
「薬局長が守られれば、薬局全体が守られる」
現場の“声にならない悩み”を形にしました。
📘 書籍情報
-
- 書名:薬局長のためのモンスター社員対応マニュアル
- 著者:ゆずまる薬局長
- 発行:YUZUMARU WORKS
- フォーマット:Kindle電子書籍
- シリーズ:薬局マネジメント・シリーズ Vol.2
📕 シリーズ第1弾はこちら
👉 『薬局長になったら最初に読む本』
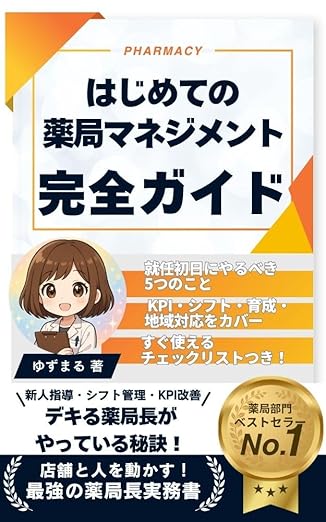






薬剤師向け転職サービスの比較と特徴まとめ


今日は、特徴をわかりやすく整理しつつ、読んでくださる方が自分の働き方を見つめ直しやすいようにまとめていきましょう。
働く中で、ふと立ち止まる瞬間は誰にでもあります
薬剤師として日々働いていると、忙しさの中で気持ちに余裕が少なくなり、
「最近ちょっと疲れているかも…」と感じる瞬間が出てくることがあります。
- 店舗からの連絡に、少し身構えてしまう
- 休憩中も頭の中が業務のことでいっぱいになっている
- 気づけば仕事中心の生活になっている
こうした感覚は、必ずしも「今の職場が嫌い」というわけではなく、
「これからの働き方を考えてもよいタイミングかもしれない」というサインであることもあります。
無理に変える必要はありませんが、少し気持ちが揺れたときに情報を整理しておくと、
自分に合った選択肢を考えるきっかけになることがあります。
薬剤師向け転職サービスの比較表
ここでは、薬剤師向けの主な転職サービスについて、それぞれの特徴を簡潔に整理しました。
各サービスの特徴(概要)
ここからは、上記のサービスごとに特徴をもう少しだけ詳しく整理していきます。ご自身の希望と照らし合わせる際の参考にしてください。
・薬剤師向けの転職支援サービスとして、調剤薬局やドラッグストアなどの求人を扱っています。
・面談を通じて、これまでの経験や今後の希望を整理しながら話ができる点が特徴です。
・「まずは話を聞いてみたい」「自分の考えを整理したい」という方にとって、利用しやすいスタイルと言えます。
・全国の薬局・病院・ドラッグストアなど、幅広い求人を取り扱っています。
・エリアごとの求人状況を比較しやすく、通勤圏や希望地域に合わせて探したいときに役立ちます。
・「家から通いやすい範囲で、いくつか選択肢を見比べたい」という方に向いているサービスです。
・調剤薬局の求人を多く扱い、条件の調整や個別相談に力を入れているスタイルです。
・勤務時間、休日日数、年収など、具体的な条件について相談しながら進めたい人に利用されています。
・「働き方や条件面にしっかりこだわりたい」方が、検討の材料として使いやすいサービスです。
・調剤系の求人を取り扱う転職支援サービスです。
・職場の雰囲気や体制など、求人票だけではわかりにくい情報を把握している場合があります。
・「長く働けそうな職場かどうか、雰囲気も含めて知りたい」という方が検討しやすいサービスです。
・薬剤師に特化した職業紹介サービスで、調剤薬局・病院・ドラッグストアなど幅広い求人を扱っています。
・公開されていない求人(非公開求人)を扱っていることもあり、選択肢を広げたい場面で役立ちます。
・「いろいろな可能性を見比べてから考えたい」という方に合いやすいサービスです。
・調剤薬局を中心に薬剤師向け求人を取り扱うサービスです。
・研修やフォロー体制など、就業後を見据えたサポートにも取り組んでいる点が特徴です。
・「現場でのスキルや知識も高めながら働きたい」という方が検討しやすいサービスです。
気持ちが揺れるときは、自分を見つめ直すきっかけになります
働き方について「このままでいいのかな」と考える瞬間は、誰にでも訪れます。
それは決して悪いことではなく、自分の今とこれからを整理するための大切なサインになることもあります。
転職サービスの利用は、何かをすぐに決めるためだけではなく、
「今の働き方」と「他の選択肢」を比較しながら考えるための手段として活用することもできます。
情報を知っておくだけでも、
「いざというときに動ける」という安心感につながる場合があります。


「転職するかどうかを決める前に、まずは情報を知っておくだけでも十分ですよ」ってお伝えしたいです。
自分に合う働き方を考える材料が増えるだけでも、少し気持ちがラクになることがありますよね。
無理に何かを変える必要はありませんが、
「自分にはどんな可能性があるのか」を知っておくことは、将来の安心につながることがあります。
気になるサービスがあれば、詳細を確認しながら、ご自身のペースで検討してみてください。

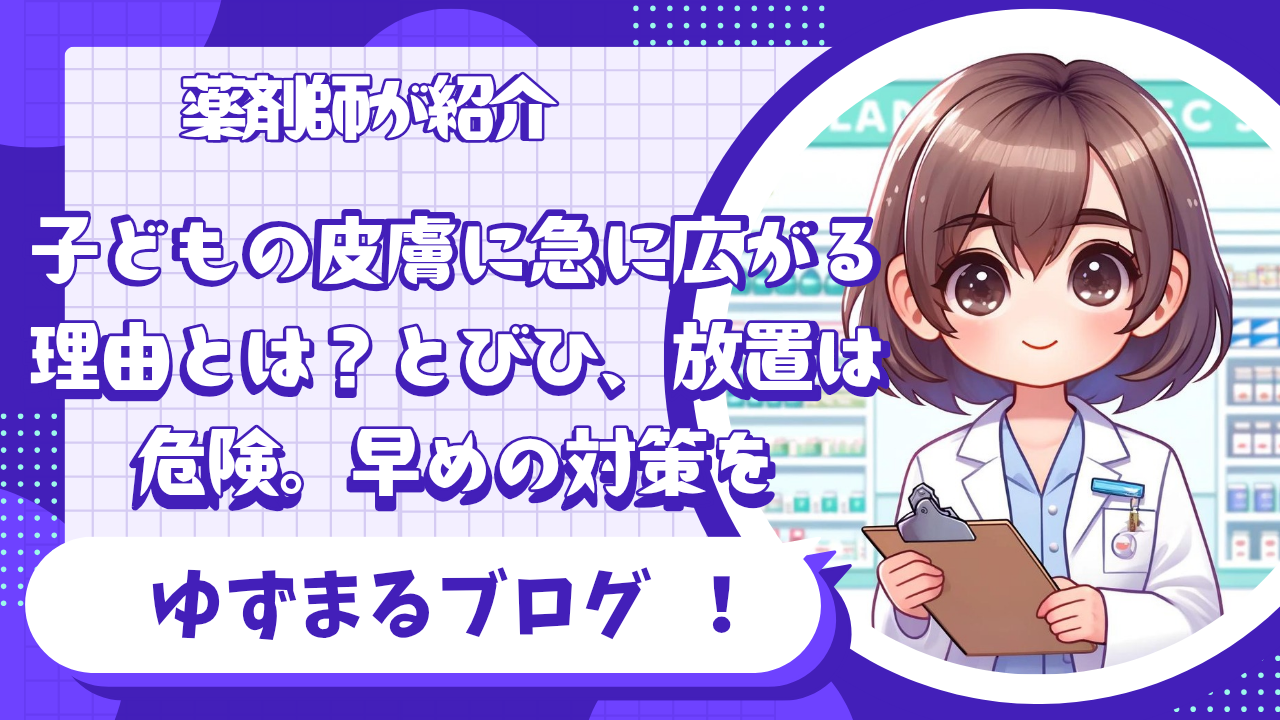


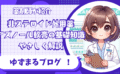
コメント