

造影剤の基本と分類
CTで使う:ヨード造影剤
- 浸透圧:高浸透圧/低浸透圧/等浸透圧。現在は低〜等浸透圧が主流。
- 投与経路:静注(経口や経管も一部検査で使用)。
- 主な注意:アレルギー様反応、造影剤腎障害(CIN/CI-AKI)。
MRIで使う:ガドリニウム造影剤
- 化学構造:線状型と環状型。一般に環状型のほうが安定で安全性が高いとされる。
- 主な注意:重度腎機能低下での腎性全身性線維症(NSF)リスク。
副作用リスクと初期対応
アレルギー様反応(即時型)
- 軽度:蕁麻疹、掻痒感、軽い紅斑。
- 中等度:顔面浮腫、喉の違和感、嘔気・嘔吐、気管支攣縮。
- 重度:呼吸困難、血圧低下、ショック。
既往のある患者、重症喘息、強いアレルギー体質ではリスク増。前投薬(抗ヒスタミン薬、必要に応じステロイド)や施設内救急体制の確認が重要。
遅発性皮膚反応
数時間〜数日後に発疹・掻痒・発熱など。自己判断で放置せず、受診を案内。
造影剤アレルギーがある人は検査できない?
「造影剤アレルギー=必ず検査不可」ではありません。
過去の反応(症状の種類・重症度)と検査の必要性を踏まえて、実施可否や対策が決まります。
軽度の反応(発疹・かゆみ など)
- 造影剤使用が可能な場合があります。
- 前処置(抗ヒスタミン薬、必要に応じてステロイド)を行って検査することがあります。
- 非イオン性・低(等)浸透圧の造影剤へ切替を検討。
中等度の反応(喘鳴、呼吸苦、顔面浮腫 など)
- 原則慎重対応。リスクとベネフィットを比較します。
- 前処置の強化、造影剤の種類変更、救急対応体制の確認が必要。
重度の反応(アナフィラキシー、ショック など)
- 原則禁忌。再投与は生命に危険が及ぶ可能性があります。
- 必要時は非造影の代替検査(超音波、MRI非造影、PET 等)を検討。
患者さんへの伝え方(薬局でのポイント)
- 過去の反応を具体的に(症状・時期・治療内容)申告してもらう。
- 「自己判断で中止・再開しない」「医師の指示に従う」ことを強調。
- 検査当日は体調を整え、異変があれば速やかに連絡するよう案内。
まとめ:アレルギー既往があっても軽症なら対策下で実施可のことあり。
重症既往は原則禁忌で、非造影の代替検査を検討します。
腎機能への影響:CIN/CI-AKIとNSF
ヨード造影剤と腎障害(CIN/CI-AKI)
- リスク因子:既存のCKD、eGFR低値、糖尿病、高齢、脱水、造影剤大量使用、反復投与、心不全、腎毒性薬併用など。
- 予防:最新の腎機能確認、十分な補液、必要最小量での投与、反復検査の間隔調整。
ガドリニウム造影剤とNSF
- 重度腎機能低下(eGFR < 30)や透析患者で注意。より安全性の高い剤形(環状型)を優先し、適応を厳格化。
腎機能低下の人は造影検査できない?(結論とポイント)
結論:「腎機能低下=必ず検査不可」ではありません。
eGFR・造影剤の種類・検査の必要性で可否と対策が決まります。必要時は代替検査(非造影MRI/CT、超音波など)も検討されます。
eGFR別の基本方針(目安)
| eGFR (mL/min/1.73m²) | CT(ヨード造影剤) | MRI(ガドリニウム造影剤) | 主な対策 |
|---|---|---|---|
| ≥60 | 通常は実施可 | 通常は実施可 | 最小必要量、脱水回避、腎毒性薬の確認 |
| 30〜59 | 多くは実施可(慎重) | 多くは実施可(慎重) | 最新の腎機能確認、十分な補液、反復投与間隔の調整 ※メトホルミンは一時休薬→48時間後に腎機能安定確認し再開を検討(施設方針による) |
| <30 | 原則慎重(回避を検討) | 原則回避(やむを得ない場合は環状型を最小量で) | 厳重管理下での適応判断、代替検査の検討、必要最小量・補液・救急体制確認 |
| 透析中 | 実施可否は個別判断(直後透析計画のことあり) | 原則回避(NSF懸念)。やむを得ない場合は専門科で厳密運用 | 担当科と連携しスケジュール調整・用量最小化 |
薬局で伝えたい要点
- 「腎機能が悪い=絶対ダメ」ではなく、必要性とリスクのバランスで決まる。
- 直近の採血(eGFR)、既往歴、常用薬(特にNSAIDs・利尿薬・メトホルミン等)を正確に申告。
- 検査後は普段どおりの飲水を心がけ、尿量減少・息切れ・強い倦怠感など異変があれば早めに受診。
まとめ:腎機能低下があっても実施できるケースは多い。ただし
eGFRが低いほど慎重に。疑問点は検査前に医療機関へ相談しましょう。
メトホルミン服用患者への対応
造影剤(特にヨード造影剤)による一過性の腎機能悪化で、メトホルミンの体内蓄積→乳酸アシドーシスリスクが理論上高まるため、eGFRに基づく休薬・再開の運用が推奨されます(施設方針に従う)。
| eGFR(mL/min/1.73m²) | メトホルミン | 造影前の対応 | 造影後の対応 |
|---|---|---|---|
| ≧60 | 通常継続可 | 脱水回避、腎機能値の確認。 | 通常は継続。体調不良・嘔吐・下痢があれば再評価。 |
| 30〜59 | 一時休薬を考慮 | 検査当日〜直前で中止する施設が多い。主治医指示に厳密に従う。 | 48時間後に腎機能を再確認し、安定を確認して再開。 |
| <30 | 原則禁忌 | ヨード造影は原則回避。どうしても必要なら専門科で厳密管理。 | 検査後もメトホルミンは再開しない(禁忌)。 |
※ カテーテル検査など動脈内投与では、eGFRが保たれていてもより慎重な運用(当日中止・48時間後再開)が選択されることがあります。施設プロトコールに準拠してください。
患者説明に使える一言メモ
- 自己判断でメトホルミンを止めたり再開したりしない。
- 検査当日は水分を十分に。嘔吐や下痢があれば連絡。
- 息切れ、強いだるさ、筋肉痛、腹痛、著しい倦怠など異変は早めに受診。
薬局での患者対応:そのまま使える会話例


主治医の指示があるはずなので、自己判断で中止・再開はしないでください。検査後は水分をしっかり摂り、体調変化があれば早めに受診しましょう。」
検査前後のセルフケアとチェックリスト
検査前チェック
- 最近の腎機能(eGFR)を把握済み?
- 造影剤や薬剤のアレルギー歴は?喘息はコントロール良好?
- 脱水を避ける(前日から普段どおりの飲水を)。
- 腎毒性薬(NSAIDsなど)常用は?主治医の指示に従う。
検査後チェック
- 当日は普段どおりに飲水(心不全等で制限がある方は医師指示優先)。
- 発疹、息苦しさ、排尿減少などあれば速やかに受診。
- メトホルミン再開は48時間後の腎機能安定確認後(医師指示)。
症例:eGFR 42でメトホルミン内服中のCT造影
70歳男性。2型糖尿病でメトホルミン継続中。CT造影検査予定、最新eGFR 42 mL/min/1.73m²。
- 方針:必要最小量の低〜等浸透圧ヨード造影剤を計画、点滴補液併用。
- メトホルミン:検査前から一時中止、48時間後に腎機能を再評価し、安定を確認して再開。
- 教育:飲水確保、異変時の連絡、自己判断での再開禁止。
まとめ
- 造影剤は診断価値が高い一方、アレルギー様反応と腎機能への影響に注意。
- メトホルミンはeGFRベースで休薬・再開を判断。原則、30未満は禁忌。
- 薬局では「自己判断で止めない」「飲水」「異変時受診」を簡潔に伝える。
造影剤×薬局実務クイズ
Q1. ヨード造影剤で比較的リスクが低いとされるのはどれ?
- 高浸透圧・イオン性
- 低(等)浸透圧・非イオン性
- 高浸透圧・非イオン性
- 低浸透圧・イオン性
正解:2
現在主流は低(等)浸透圧・非イオン性ヨード造影剤で、アレルギー様反応やCINリスク低減が期待されます。
Q2. メトホルミン内服中でCT造影予定。eGFR 45の患者の対応で適切なのは?
- 中止不要。いつも通り継続。
- 自己判断で2倍量内服する。
- 主治医の指示で一時休薬し、48時間後に腎機能安定を確認して再開。
- 永久中止。
正解:3
eGFR 30〜59では一時休薬を考慮し、造影後48時間で腎機能を再確認して再開する運用が一般的です。
Q3. ガドリニウム造影剤でNSFリスクが低いとされる構造は?
- 線状型(linear)
- 環状型(macrocyclic)
正解:2
環状型はキレート安定性が高く、重度腎機能低下例でのNSFリスクがより低いとされています。
Q4. 造影剤アレルギー既往がある患者の再検査について正しいのは?
- どんな既往でも再投与は不可能。
- 軽度既往なら前処置などの対策下で実施可能な場合がある。
- 重度既往でも造影剤を変えれば必ず安全。
- 前処置は禁忌。
正解:2
軽度のアレルギー既往では非イオン性造影剤や前処置で検査可能ですが、アナフィラキシーなど重度既往は原則禁忌です。
Q5. CIN(造影剤腎症)の予防で基本的な対策は?
- 造影剤量を増やす。
- 補液+腎機能確認+必要最小量で投与。
- NSAIDsを追加。
- 検査前は飲水禁止。
正解:2
最新の腎機能確認、十分な補液、必要最小量での投与がCINリスク低減の基本です。NSAIDsは腎毒性のため避けます。
よくある質問
造影剤アレルギーがあると検査は受けられない?
重篤既往では中止・代替検査を検討。軽度既往では前投薬のうえ実施されることも。施設方針に従います。
腎臓が悪い人は造影剤を使えない?
eGFR 30未満では慎重適応(または回避)ですが、リスクとベネフィットを比較し、必要なら対策を取って実施されます。
授乳中でも造影検査は大丈夫?
母乳移行は極少量とされ、多くのガイドラインで授乳継続が許容されます。施設によって24時間中止案内を行う場合も。
メトホルミンはいつ再開する?
目安は48時間後に腎機能が安定であることを確認してから。必ず医師の指示に従ってください。
参考文献
- 日本医学放射線学会『造影剤安全指針 2023』https://www.radiology.jp/ 最終確認日: 2025-09-16
- 厚生労働省 造影剤関連ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000183318.html 最終確認日: 2025-09-16
- ACR Manual on Contrast Media(最新版)https://www.acr.org/Clinical-Resources/Contrast-Manual 最終確認日: 2025-09-16
- ESUR Contrast Media Safety Committee. Guidelines. https://www.esur.org/guidelines 最終確認日: 2025-09-16
- 日本糖尿病学会『糖尿病治療ガイド 2024』南江堂(eGFRとメトホルミン使用基準の確認)
薬局で働いていると、どうしても避けられないのが「人間関係のストレス」。 そんな現場のリアルな悩みに向き合うために、管理薬剤師としての経験をもとにまとめたのが、この一冊です。 『薬局長のためのモンスター社員対応マニュアル』 薬局で起こりやすい“モンスター社員”を15タイプに分類し、 薬局で人に悩まないための「実践マニュアル」として、 「薬局長が守られれば、薬局全体が守られる」 📕 シリーズ第1弾はこちら 📘『薬局長のためのモンスター社員対応マニュアル』発売のお知らせ
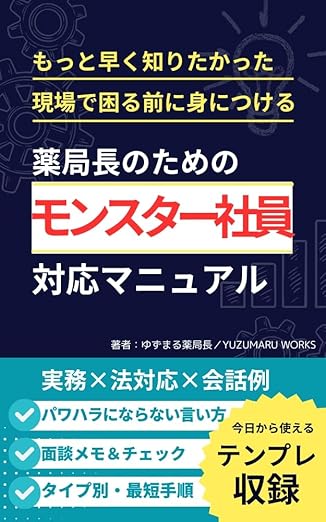
患者対応、スタッフ教育、シフト調整……。
気がつけば、薬局長がいちばん疲れてしまっている。





― 現場で困る前に身につける 実務 × 法対応 × 会話例 ―
それぞれの特徴・対応法・指導会話例を紹介。
パワハラにならない注意方法や、円満退職・法的リスク回避の実務ステップも具体的に解説しています。
日々の業務の支えになれば幸いです。
現場の“声にならない悩み”を形にしました。
📘 書籍情報
👉 『薬局長になったら最初に読む本』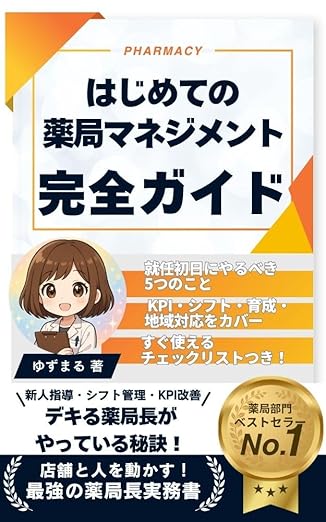







もっと自信を持って説明できるようになりたいです。

透析特有の薬物動態や電解質管理が体系化されて、薬局でも“腎に強い薬剤師”になれるよ🍃
疑義照会やトレーシングレポートの説得力がぐっと上がります。
- 吸着剤・リン吸着薬/ビタミンD製剤/Ca製剤の使い分け
- 高K血症・低Ca血症などのリスク説明と服薬支援
- バンコマイシン等の用量調整と投与タイミングの考え方
- 電解質管理と食事・薬物の相互作用の押さえどころ
- 抗菌薬・抗凝固薬の調整ロジック(透析日との関係)
- 患者さんに伝わる数値の読み方とセルフケア支援



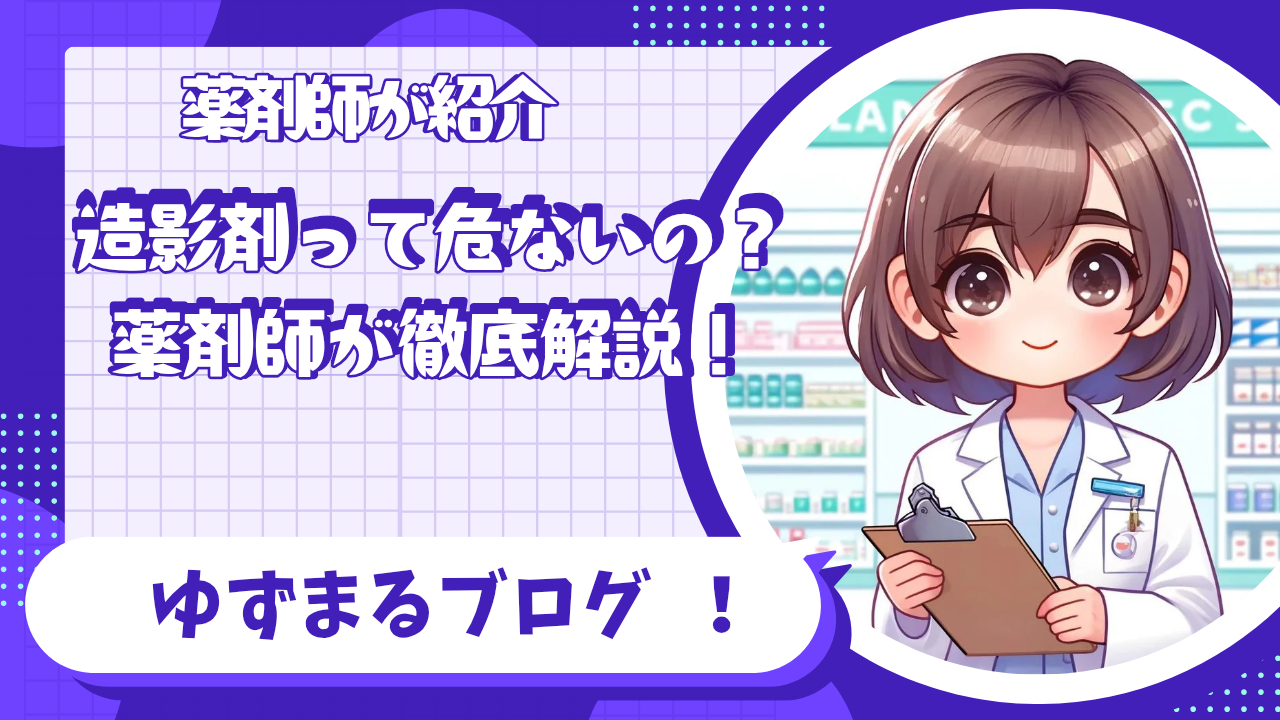

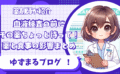
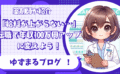
コメント