

この記事では、「咳喘息(Cough-variant asthma)」について医学的に詳しく、薬剤師・医療従事者の視点で深掘りします。前編では主に病態・発症機序・診断・鑑別までを徹底的に解説します。
- 咳喘息とは:定義と臨床的特徴
- 発症メカニズム(病態生理)
- 気道過敏性と咳反射の亢進
- 疫学・発症背景
- 咳喘息の臨床症状
- 鑑別診断(慢性咳嗽の主要疾患)
- 診断の流れ
- 治療的診断(ICS反応性)
- 検査まとめ表
- 診断のピットフォール(よくある誤診)
- まとめ(前編)
- 咳喘息の治療方針
- 治療の基本構造
- 主要薬剤の分類と薬理作用
- 吸入薬の比較表
- 服薬指導とアドヒアランス支援
- 症例で学ぶ治療実践
- PR|資格・スキルアップで呼吸管理を極める
- まとめ(中編)
- 薬局実務での対応ポイント
- 年齢別・対象別の対応
- 慢性咳嗽全体での位置づけ(ガイドライン2025より)
- 難治例へのアプローチ
- 患者教育リーフレットに入れるべき内容
- 在宅・地域連携の工夫
- 薬局での患者への説明フレーズ集
- まとめ(後編)
- よくある質問(FAQ)
- 参考文献
咳喘息とは:定義と臨床的特徴
咳喘息(せきぜんそく)は、喘鳴や呼吸困難を伴わず、慢性的に咳のみが続く喘息の一亜型です。正式には cough-variant asthma(CVA) と呼ばれます。
- 成人の慢性咳嗽の原因の中で約20〜40%を占める。
- 夜間や早朝に乾いた咳が悪化するのが特徴。
- 咳止めが効かず、吸入ステロイドで改善する。
- 放置すると約30〜40%が典型的喘息へ移行する。
発症メカニズム(病態生理)
咳喘息は、気道粘膜における慢性炎症が基盤です。病理的には喘息と共通する部分が多く、特に以下の細胞・メディエーターが関与します。
1. 炎症細胞の関与
- 好酸球:主要な炎症担当細胞。IL-5, IL-13 などのサイトカインで活性化され、気道上皮を障害。これが咳受容体を感作させる。
- 肥満細胞:ヒスタミン、ロイコトリエンC4, D4, E4を放出し、気道平滑筋収縮を誘発。
- T細胞(特にTh2細胞):IL-4, IL-5, IL-13を介してアレルギー炎症を維持。
- 上皮細胞:アレルゲン刺激でIL-33やTSLPを放出し、炎症連鎖を活性化。
2. 炎症メディエーター
気道過敏性亢進には以下のメディエーターが関与します。
- ロイコトリエン:気道収縮・粘液分泌・血管透過性亢進。
- ヒスタミン:知覚神経への刺激による咳反射促進。
- プロスタグランジンD2:血管拡張と炎症細胞遊走。
- サブスタンスP・ニューロキニンA:感覚神経を介して咳反射閾値を低下。
つまり、「好酸球性炎症+神経感作」が咳喘息の病態を作ると考えられています。
気道過敏性と咳反射の亢進
咳喘息患者では、気道上皮障害によって感覚神経(C線維やRARs:rapidly adapting receptors)が過敏になります。わずかな刺激(冷気、臭気、乾燥空気など)でも、迷走神経経路を介して咳反射が誘発されるようになります。
疫学・発症背景
- 発症年齢:成人で20〜50代が多い。
- 性差:女性にやや多い(特に非喫煙女性)。
- 誘因:ウイルス感染後、花粉やダニ、冷気、香水、タバコ煙、ストレスなど。
- 季節性:春・秋に多い。
- 併存疾患:アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、胃食道逆流症(GERD)など。
咳喘息の臨床症状
- 持続する乾いた咳(痰が少ない)
- 夜間・早朝に悪化しやすい
- 運動や会話、冷気吸入で誘発される
- 呼吸困難・喘鳴は通常認めない
- 咳止め薬では改善しにくい
鑑別診断(慢性咳嗽の主要疾患)
| 疾患 | 特徴 | 区別のポイント |
|---|---|---|
| アトピー咳嗽 | アトピー体質、FeNO高値、咳のみ | ICS無効なことも多く、抗ヒスタミン薬が有効 |
| 後鼻漏(上気道咳嗽症候群) | のどの違和感、鼻閉、後鼻漏感 | 抗ヒスタミン薬・鼻炎治療で改善 |
| 胃食道逆流症(GERD) | 夜間悪化、胸やけ・呑酸 | PPIで改善、ICS無効 |
| 感染後咳嗽 | 風邪後数週間持続 | 自然軽快傾向、ICS不要 |
| ACE阻害薬性咳嗽 | 降圧薬服用後に咳出現 | 薬剤中止で改善 |
診断の流れ
2025年版「咳嗽・喀痰診療ガイドライン」に基づく咳喘息の診断フローを要約します。
- 問診・病歴聴取:発症時期、誘因、服薬歴、生活環境。
- 除外診断:胸部X線で肺炎・腫瘍などを除外。
- 呼吸機能検査:スパイロメトリーで気流制限を確認(多くは正常)。
- FeNO測定:25ppb以上なら好酸球性炎症を示唆。
- 気道可逆性試験:β₂刺激薬投与で1秒量(FEV₁)が改善すれば喘息型を支持。
- 治療的診断:ICS導入で症状が改善すれば確定的。
治療的診断(ICS反応性)
吸入ステロイドを2〜4週間使用し、咳が軽減したら診断確定とします。改善しない場合は他疾患(GERD、後鼻漏、アトピー咳嗽など)を再評価。
検査まとめ表
| 検査 | 目的 | 所見 |
|---|---|---|
| 胸部X線 | 重篤疾患除外 | 正常 |
| スパイロメトリー | 気流制限確認 | 多くは正常 |
| FeNO | 好酸球性炎症 | 上昇 |
| 可逆性試験 | 気道収縮可逆性 | 陽性 |
| メサコリン試験 | 気道過敏性 | 陽性(感度高) |
| 血液好酸球 | アレルギー背景 | 軽度上昇 |
診断のピットフォール(よくある誤診)
- 「風邪が長引いている」と放置 → 実は咳喘息。
- 「喘鳴がないから喘息ではない」と誤解。
- 「咳止めが効かない=難治性咳嗽」と短絡。
- アトピー咳嗽・GERDとの鑑別が不十分。
- 吸入手技エラーで「ICS無効」と判断。
これらを避けるためには、除外+ICS反応性の確認が最も重要です。
まとめ(前編)
- 咳喘息は咳のみを主症状とする喘息型。
- 好酸球性炎症と気道過敏性が病態の中心。
- 診断は除外診断と治療的診断を組み合わせる。
- FeNO測定やICS反応性が決め手になる。


咳喘息の治療方針
治療の目的は次の3点です。
- 咳症状の速やかな軽減
- 気道炎症の鎮静と再発防止
- 気管支喘息への進展予防
ガイドライン(JGL2024、咳嗽診療GL2025)では、咳喘息は「軽症持続型喘息に準じた治療」とされ、吸入ステロイド薬(ICS)を基本とします。
治療の基本構造
治療は「段階的ステップアップ/ステップダウン」モデルを採用します。
| ステップ | 治療内容 | ポイント |
|---|---|---|
| Step 1 | ICS単剤 | 軽症例の初期治療。2〜4週で改善しなければ次へ。 |
| Step 2 | ICS/LABA配合剤 or ICS+LTRA | 夜間咳・運動誘発性に対応。アドヒアランス改善にも。 |
| Step 3 | ICS増量+追加治療(LAMA, 抗ロイコトリエンなど) | 難治・再燃例。 |
| Step 4 | 短期経口ステロイド or 専門医紹介 | 重症例・コントロール不良例。 |
主要薬剤の分類と薬理作用
1. 吸入ステロイド薬(ICS)
最も重要な抗炎症治療。好酸球性炎症を抑え、咳受容体の感作を改善します。
- 薬理作用:グルココルチコイド受容体を介してサイトカイン産生抑制(IL-4, IL-5, IL-13など)。好酸球浸潤を抑制。
- 主な製剤:フルチカゾン、ブデソニド、モメタゾン、シクレソニド、ベクロメタゾンなど。
- 用法例:1日1〜2回吸入。咳喘息では通常用量で開始。
- 副作用:口腔カンジダ、嗄声、咽頭刺激。対策はうがい+スペーサー使用。
ICSは咳喘息治療の第一選択。2週間〜1か月で改善が見られなければ、吸入手技・継続性を確認します。
2. ICS/LABA配合剤
ICS単剤で不十分な場合に用います。LABA(長時間作用型β₂刺激薬)が気道平滑筋を弛緩させ、咳誘発を軽減します。
| 配合剤 | 成分 | 特徴 |
|---|---|---|
| アドエア/フルティフォーム | フルチカゾン+サルメテロール/ホルモテロール | 1日2回。しっかりした咳抑制効果。 |
| シムビコート | ブデソニド+ホルモテロール | 頓用併用(SMART療法)も可。 |
| ブレオ | フルチカゾン+ビランテロール | 1日1回。高いアドヒアランス。 |
配合剤はデバイスが使いやすく、継続率が高いという利点があります。
3. 抗ロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRA)
ロイコトリエンD4受容体を阻害し、炎症・平滑筋収縮を抑制します。ICSで不十分な症例、鼻炎併発例に有用。
- 代表薬:モンテルカスト(シングレア)、プランルカスト(オノン)
- 1日1回(就寝前投与が多い)
- 副作用:肝機能異常、頭痛、神経症状(稀)
4. SABA(短時間作用型β₂刺激薬)
咳発作時の頓用薬。2〜4時間作用します。
- 代表薬:サルブタモール(メプチン)、プロカテロール(オーキシス)
- 注意:週2回以上使用はコントロール不良のサイン。
5. 経口ステロイド
重症・難治例や急性増悪時に短期間使用。
- プレドニゾロン5〜10mg/日を5〜7日間
- 長期使用はリスク(感染・骨粗鬆症・高血糖)
6. 新規薬:P2X3受容体拮抗薬(ゲーファピキサント)
難治性慢性咳嗽に対して承認。感覚神経のATP受容体(P2X3)を遮断し、咳反射を抑制します。
- 製品名:リフヌア錠45mg(MSD)
- 用量:1回45mg、1日2回
- 副作用:味覚障害(40〜60%)
- 適応:咳喘息そのものの一次治療ではないが、難治例では専門医で検討可能。
吸入薬の比較表
| 製剤名 | 分類 | 回数 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| フルタイド | ICS単剤 | 1〜2回 | 吸入音静か。初期治療に適。 |
| ブレオ | ICS/LABA | 1回 | 高アドヒアランス。味刺激少。 |
| シムビコート | ICS/LABA | 1〜2回 | 頓用も可。即効性。 |
| アドエア | ICS/LABA | 2回 | 安定したコントロール。 |
| シングレア | LTRA | 1回(経口) | 鼻炎併発例にも。 |
服薬指導とアドヒアランス支援
1. 吸入手技の確認ポイント
- 吸気速度(MDIはゆっくり、DPIは速く)
- 吸入後の息止め(5〜10秒)
- 吸入後のうがい(ICS必須)
- デバイス洗浄の有無・頻度
1回の誤吸入でも効果が出にくくなるため、初回は必ず実演確認を。
2. 継続服薬の動機づけ
- 「咳が止まっても炎症は残っています」
- 「ICSは炎症を鎮める治療。即効性はありません」
- 「続けることで再発を防ぎます」
3. 環境と生活の調整
- 禁煙・受動喫煙の回避。
- 香水・柔軟剤など強香性物質を避ける。
- 寝室を清潔に保ち、湿度40〜60%に管理。
- 冷気吸入対策としてマスク着用。
症例で学ぶ治療実践
症例1:風邪後に咳が2か月続く30代女性
FeNO 40ppb、肺機能正常。ICS(フルチカゾン100μg 1日2回)開始。2週後に夜間咳改善、4週で寛解。3か月継続してステップダウン。
症例2:香料で咳が悪化する20代女性
職場での香水・柔軟剤がトリガー。ICS/LABAにLTRAを追加し、環境改善指導。咳発作消失。
症例3:GERD合併の40代男性
ICS効果不十分。夜食・アルコール控え、PPI併用で改善。咳喘息+GERDの併存例では両方を治療。
症例4:再燃を繰り返す50代女性
ICS中止直後に再燃。シムビコートへ切り替え、半年間継続。咳完全消失後に漸減成功。
PR|資格・スキルアップで呼吸管理を極める
まとめ(中編)
- ICSが治療の軸。反応不十分なら配合剤またはLTRA追加。
- 手技ミス・アドヒアランス不良が最大の落とし穴。
- 頓用β₂刺激薬の頻用は危険信号。
- 再燃予防には少なくとも3か月以上の継続を。
- 環境因子・合併症(GERD、鼻炎)を同時にケア。
次の後編では、小児・高齢者・妊婦への配慮、実務・トレーシングレポート・算定コメント例、そして最新ガイドライン解説を扱います。


薬局実務での対応ポイント
1. 吸入薬の処方確認
- デバイス変更があった場合は「操作説明済みか」要確認。
- 前回ICS単剤→今回配合剤になっている場合は、医師意図を患者説明に反映。
- 頓用β₂刺激薬の追加はコントロール不良のサイン。医師へフィードバック。
- LTRA追加はアレルギー背景強いサイン。季節性・通年性の確認。
2. 服薬フォローアップ・記録例
フォローアップ日:処方2〜4週後を目安。吸入継続と症状変化を確認。
【フォロー記録例】
ICS開始2週後。夜間咳は半減。吸入1日2回実施、手技良好。副作用なし。
ICS継続の重要性とうがい指導を再確認。ステップダウン時期は医師判断に委ね。
3. トレーシングレポート例
【内容】
夜間咳再燃、頓用吸入週3回。DPI吸入で吸気流速弱く、息止め5秒未満。
ブレオからシムビコートへの変更検討を提案。吸入動画QR案内済み。
4. 算定コメント例
- 「吸入手技の確認と再指導を実施。うがい励行指導済み。」
- 「ICS継続の必要性を説明。服薬アドヒアランス良好。」
- 「頓用吸入の頻度増加。医師へフィードバック予定。」
年齢別・対象別の対応
1. 小児の咳喘息
- 発症年齢:3〜10歳に多い。
- 夜間・早朝の咳が主症状。多くは風邪後発症。
- 吸入ステロイドが基本(年齢に応じたデバイスを選択)。
- ICSで改善しない場合はアトピー咳嗽、上気道炎症を再評価。
- 過剰な鎮咳薬使用は避ける。
2. 高齢者の咳喘息
- 吸入操作が難しく、デバイス選択と手技確認が極めて重要。
- 骨粗鬆症・糖尿病合併例ではICSの長期副作用に留意。
- 誤嚥性咳嗽・心不全性咳嗽との鑑別を忘れない。
- 咳が原因で睡眠障害やADL低下を招くケースも。
3. 妊婦・授乳婦の咳喘息
- 妊娠中もICSは基本的に安全(吸入による全身移行は微量)。
- フルチカゾン、ブデソニドが安全性データ豊富。
- LABA併用も有用だが、最低限の用量で。
- LTRA(モンテルカスト)は妊婦・授乳婦でも比較的安全報告あり。
- 未治療の喘息・咳喘息は低酸素血症を招くため、治療継続が母児ともに安全。
慢性咳嗽全体での位置づけ(ガイドライン2025より)
2025年版「咳嗽・喀痰診療ガイドライン」では、慢性咳嗽を以下の3群に分類しています。
| 分類 | 主な疾患 | 治療の柱 |
|---|---|---|
| ① 炎症性咳嗽 | 咳喘息、アトピー咳嗽 | ICS・LTRAなど抗炎症治療 |
| ② 感覚神経過敏性咳嗽 | 難治性慢性咳嗽、リフヌア適応 | P2X3拮抗薬 |
| ③ その他 | GERD、後鼻漏、薬剤性など | 原因治療 |
咳喘息は炎症性咳嗽の代表。適切な抗炎症治療が第一歩です。
難治例へのアプローチ
- 吸入手技・服薬確認 → 問題なければFeNO再測定。
- 併存疾患(GERD、副鼻腔炎、アトピー咳嗽)を再評価。
- 必要に応じてLTRA追加、ICS増量、配合剤への変更。
- それでも不十分な場合、専門医でP2X3拮抗薬や生物学的製剤を検討。
患者教育リーフレットに入れるべき内容
- 「咳が止まっても3か月は治療を続けましょう」
- 「吸入薬はのどに当てないように。息を止めて吸い込みます」
- 「吸入後は必ずうがいを」
- 「冷気・におい・タバコ煙に注意」
- 「夜間咳が増えたら、無理せず受診を」
在宅・地域連携の工夫
- 在宅酸素・訪問看護対象患者でもICSは継続可能。
- 服薬支援:ピルケースに「朝/夜」ラベルを貼る。
- 訪問薬剤管理で吸入デモ実施可。
- 連携ツール:吸入動画リンク、QRコード付きチラシ。
薬局での患者への説明フレーズ集
- 「咳喘息は“音のしない喘息”。気道の炎症が原因です。」
- 「咳止めでは治りません。炎症を抑える吸入が必要です。」
- 「続けることで、再発や喘息移行を防げます。」
- 「うがいを忘れずに。1回の吸入がとても大切です。」
- 「夜の咳が再び出たら早めに相談を。」
まとめ(後編)
- 咳喘息は慢性咳嗽の代表的疾患で、治療の中心はICSによる抗炎症。
- 診断は除外+治療反応性で確定。
- アドヒアランス向上と吸入手技指導が最重要。
- 小児・高齢・妊婦でも基本方針は同じだが配慮が必要。
- 難治例は専門医と連携し、P2X3拮抗薬など新規治療を検討。
よくある質問(FAQ)
Q. 咳喘息とアトピー咳嗽の違いは?
どちらも咳のみを主症状としますが、咳喘息はICSが有効で、気道過敏性亢進を伴います。アトピー咳嗽はヒスタミンH1拮抗薬やLTRAで改善しやすく、ICSが効きにくいこともあります。
Q. 咳が止まったらすぐ吸入をやめてもいい?
いいえ。炎症は目に見えません。少なくとも3か月は続けてから医師と相談のうえ段階的に減量しましょう。
Q. 吸入薬の種類が多くて混乱します。
作用は似ていますが、デバイスや回数が異なります。薬剤師に「自分の吸入器の名前」と「回数」をメモしてもらいましょう。
Q. 妊娠中のICSは大丈夫?
はい、吸入ステロイドは全身移行が微量で、胎児への影響は報告されていません。未治療による低酸素のほうが危険です。
Q. 咳が再発しやすい人の特徴は?
喫煙者、アレルギー体質、GERDや鼻炎併存、ICS早期中止例などです。生活・環境調整と継続治療で防げます。
参考文献
- 日本呼吸器学会. 咳嗽・喀痰の診療ガイドライン 第2版(2025年版)
最終確認日:2025-10-15 - 日本アレルギー学会. 喘息予防・管理ガイドライン2024(JGL2024)
最終確認日:2025-10-15 - 日本アレルギー学会. 喘息予防・管理ガイドライン2021(全文PDF)
最終確認日:2025-10-15 - MSD株式会社. リフヌア(ゲーファピキサント):難治性慢性咳嗽の選択的P2X3拮抗薬 製品情報
最終確認日:2025-10-15 - P2X3受容体拮抗薬と咳:Gefapixantに関するレビュー(アレルギー誌)
最終確認日:2025-10-15 - 難治性慢性咳嗽の診断と治療(日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌)
最終確認日:2025-10-15 - 日本小児アレルギー学会. 小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2023(Minds要旨)
最終確認日:2025-10-15 - 厚生労働省. 気管支喘息の治療目標と管理(公式資料PDF)
最終確認日:2025-10-15
📘『薬局長のためのモンスター社員対応マニュアル』発売のお知らせ
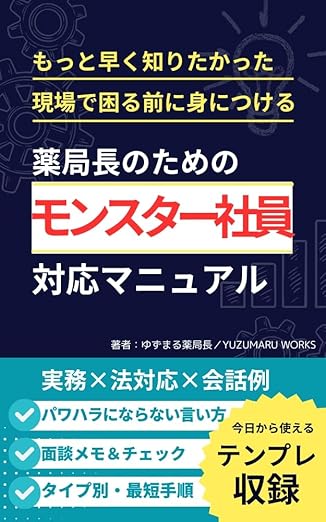
薬局で働いていると、どうしても避けられないのが「人間関係のストレス」。
患者対応、スタッフ教育、シフト調整……。
気がつけば、薬局長がいちばん疲れてしまっている。
そんな現場のリアルな悩みに向き合うために、管理薬剤師としての経験をもとにまとめたのが、この一冊です。






『薬局長のためのモンスター社員対応マニュアル』
― 現場で困る前に身につける 実務 × 法対応 × 会話例 ―
薬局で起こりやすい“モンスター社員”を15タイプに分類し、
それぞれの特徴・対応法・指導会話例を紹介。
パワハラにならない注意方法や、円満退職・法的リスク回避の実務ステップも具体的に解説しています。
- 現場によくある「人のトラブル」15パターンと対応のコツ
- パワハラにならない“安全な指導”の伝え方
- 円満退職を導くための面談・記録・法的ポイント
- 薬局長自身を守るマネジメント思考
薬局で人に悩まないための「実践マニュアル」として、
日々の業務の支えになれば幸いです。
「薬局長が守られれば、薬局全体が守られる」
現場の“声にならない悩み”を形にしました。
📘 書籍情報
-
- 書名:薬局長のためのモンスター社員対応マニュアル
- 著者:ゆずまる薬局長
- 発行:YUZUMARU WORKS
- フォーマット:Kindle電子書籍
- シリーズ:薬局マネジメント・シリーズ Vol.2
📕 シリーズ第1弾はこちら
👉 『薬局長になったら最初に読む本』
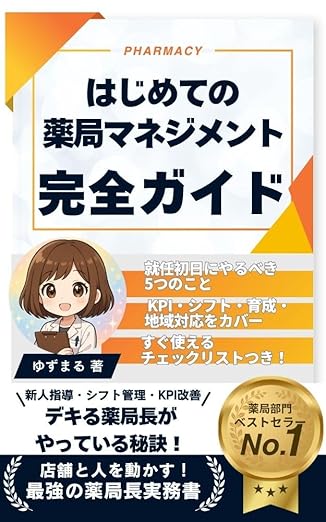








酸素療法・人工呼吸器の基本から吸入デバイス教育まで、薬局で“呼吸に強い”説明ができるようになるよ💜
吸入手技指導やデバイス選択、HOTと薬物療法の説明が一気に体系化。
- O₂流量・SpO₂目標・CO₂貯留の注意点を理解
- ICS/LABA/LAMA・SABA/SAMAの使い分けと併用
- 吸入デバイス(MDI・DPI・SMI・ネブライザ)の指導ポイント
服薬指導・在宅訪問・医療機器業者との連携まで、説明の質が跳ね上がります。
- 酸素療法の基礎(FiO₂・流量・目標SpO₂・注意点)
- 吸入薬の薬理と患者タイプ別の選び方
- デバイス別の手技チェックリスト/フォローの型



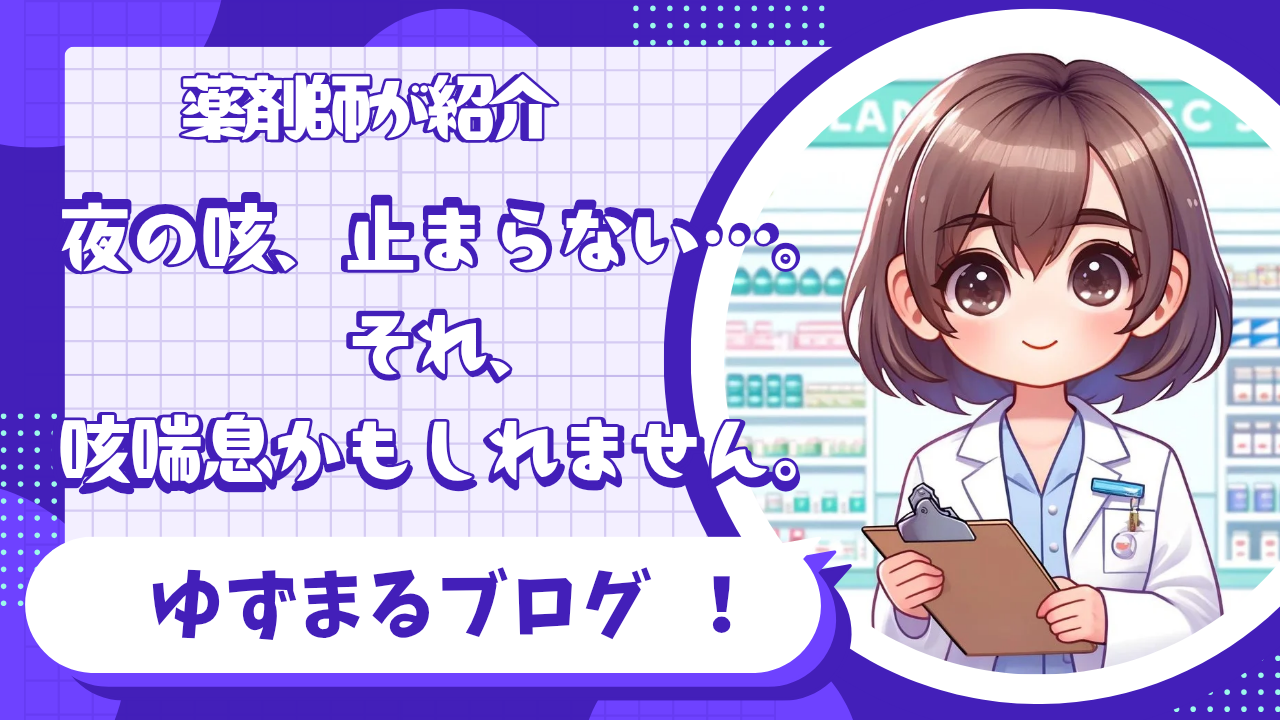

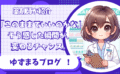

コメント