
年5件くらいやろうって話が出てるんだけど、どうすれば実現できるのか悩んでて…。

先輩、効率的にやるコツってあるんですか?

今回は「多職種会議を年5件達成する方法」をまとめてみたから、一緒に確認してみよう!
医療や介護の現場で求められる多職種連携。
その中心に位置する「多職種会議」は、患者のQOLを向上させ、チーム全体のケアの質を高めるために欠かせない取り組みです。
しかし、実際には「年○件実施しよう」という目標が掲げられても、なかなか現場でうまく機能していないケースも多いのが実情です。
本記事では、薬局薬剤師の視点から「どうすれば年5件の多職種会議を現実的に実施できるのか?」をテーマに、現場で役立つ具体的なステップと工夫を紹介します。
これから会議を定期的に始めたい施設の方や、すでに始めているけど継続が難しいと感じている方にも役立つ内容を盛り込んでいます。
計画→準備→実行→記録→評価までの流れを押さえることで、無理なく年5件の達成を目指せます。まずは身近なケースから始めていきましょう!
多職種会議とは?何のために行うの?
「多職種会議」とは、患者や利用者の生活全体を見据えた支援のために、医療・介護・福祉の異なる専門職が集まり、情報を共有し意見交換を行う場のことです。
特に在宅医療や高齢者施設の現場では、以下のような職種が関わります:
- 医師
- 薬剤師
- 看護師(訪問看護)
- ケアマネージャー
- 介護職
- リハビリ職(PT・OT・ST)
- 管理栄養士
- ソーシャルワーカー
これらの専門家が、一人の患者を中心に、「何が課題か?」「どんな支援が必要か?」をすり合わせるのが多職種会議の目的です。

なぜ今、多職種会議が重視されるのか?
高齢化や在宅医療の拡大に伴い、「1人の専門職だけで支援を完結させることが難しい時代」になっています。
それに伴い、以下のような課題が出てきます:
- 服薬管理と食事の連携不足
- 認知症による生活リズムの崩れ
- 複数主治医からの処方の重複
- 支援者間の情報共有不足による見落とし
こうした問題を解決するために、「横のつながり=多職種連携」が必須となってきており、それを具体的に形にするのが「多職種会議」です。

薬剤師が多職種会議を主導する意味とは?
これまで多職種会議というと、医師やケアマネージャーが中心になって開催するイメージが強かったかもしれません。
しかし、近年では薬剤師が「薬の専門家」として、積極的に介入し会議を主導することが求められています。
なぜ薬剤師が主導すべきなのか?
- 服薬アドヒアランスの問題は「薬剤師の視点」なしでは見落とされやすい
- ポリファーマシーや副作用の影響は、薬の整理なくして改善しない
- 薬局薬剤師が地域の患者状況を最も把握していることが多い
- 地域支援体制加算の取得・継続には「地域医療への積極的関与」が要件に含まれる

薬剤師が会議を主導する5ステップ
- 会議の目的を明確にする:服薬状況の再評価?支援方法の見直し?ゴールを定めましょう
- 対象患者を選定する:服薬に課題がある患者、多剤併用の高齢者、認知症患者など
- 関係職種に声をかける:訪問看護師、ケアマネ、医師、栄養士など
- 資料を準備する:お薬手帳、最近の処方履歴、アセスメントシートなど
- 進行を担当し、記録も残す:30〜45分を目安に効率的に進め、議事録を必ず作成
会議開催後は、内容を共有するメールや書面をまとめ、関係者にフィードバックします。これも薬剤師の重要な役割のひとつです。

次は「テーマの決め方と会議ネタの見つけ方」を紹介するね!
会議の規模はどのくらい?医師がいなくても大丈夫?
多職種会議というと「大きな会議室で、10人以上が集まるようなもの」と思われがちですが、実は「2〜3人規模」でも立派な多職種会議として評価されます。
最低限必要な「多職種」の範囲
定義としては、“異なる分野の専門職が複数名集まって患者の課題を共有し、支援方針を話し合う場”であれば、規模は問いません。
たとえばこんな組み合わせでもOKです:
- 薬剤師 + ケアマネージャー
- 薬剤師 + 訪問看護師
- 薬剤師 + 管理栄養士 + リハビリ職
「医師が参加しなければ加算や評価対象にならない」ということはありません。
ただし、医師と情報共有された形跡(報告書など)があると、より客観的な評価につながります。
厚労省の考え方:柔軟な会議形態も認められる
厚生労働省の通知では、以下のような柔軟な形態も「会議」として認められています:
- 電話・Zoom・チャットベースでの意見交換(簡易形式)
- 訪問のついでに現場で立ち話 → 内容を記録に残す
- 複数職種がメールで意見交換し、方針が一致したケース

医師の参加があるときはどう活用する?
もちろん、医師が参加できる場合は強い味方です!
処方の調整や終末期の判断などは医師の関与が必須な場面もあるため、内容に応じて「このケースは医師に同席してもらおう」と柔軟に判断しましょう。

気軽に“ミニ会議”から始めてOKなんだ〜♪
多職種会議は地域包括が主催しないといけないの?
答えはNOです。
多職種会議は、医療・介護・福祉のいずれかの専門職が「必要性を感じた時点で自主的に開催して良い」とされています。
確かに、地域包括支援センターが主体となるケースも多いですが、以下のような職種が主催しても問題ありません:
- 薬剤師(薬局)
- ケアマネージャー(居宅介護支援事業所)
- 訪問看護師
- 地域医療機関(クリニック、病院)
重要なのは「地域の関係職種が適切に連携できていること」「患者や利用者の課題に応じて、会議が実施されていること」であり、主催者の職種そのものには制限がありません。
薬局薬剤師が主催する会議も加算・評価の対象?
はい、薬局薬剤師が主導して開催した会議も、地域支援体制加算の実績や、在宅業務における評価対象となります。特に以下のような条件を満たしていれば、有効な活動と認められます:
- 複数の他職種(例:看護、介護、医師)と連携している
- 患者一人を中心に具体的な支援方針を議論している
- 議事録などの記録を残している

これなら私でも主催できそう!

会議のテーマはどう決める?ネタはどこから見つける?
多職種会議を企画するときに最も悩むのが「テーマ設定」です。
無理に全体会議にしなくても、小規模でも実施可能な「実用的なテーマ選び」がポイントになります。
テーマの探し方:日々の業務にヒントあり!
実は、毎日の業務の中に「会議の種」がたくさん隠れています。以下は薬局業務でよくあるケースです:
- 認知症患者で服薬コンプライアンスが悪い
- 多剤併用で副作用が心配される高齢者
- 家族との連携が難航している在宅患者
- 誤薬や残薬が継続的に発生しているケース
- 介護と医療の連携が途切れている退院直後の患者

具体的なテーマ例
| テーマ | 目的 |
|---|---|
| 認知症患者の服薬支援 | 生活リズムに合わせた服薬スケジュール調整 |
| 在宅酸素療法患者の薬剤整理 | 相互作用や体調変化の把握 |
| ポリファーマシーの見直し | 処方カスケードの回避と医師への提案 |
| 独居高齢者の服薬・生活支援 | 見守り体制と支援者間の連携構築 |
| 終末期患者のケア調整 | 苦痛緩和と最小限の投薬支援 |
テーマは「小さく」始めよう
最初から「全体的な在宅連携」など大きな議題を設定すると、準備が大変になります。
まずは「1人の患者」「1つの問題」に焦点を絞ると、会議もスムーズに進みます。

無理せず「この人だけのミニ会議」から始めてみよう♪
テーマは何でもいいの?地域活性化でも多職種会議になる?
はい、テーマの自由度は意外と高いです!
会議の目的が「地域住民の生活支援・健康支援・介護予防・医療連携の向上」などに関連していれば、地域活性化や健康づくりといった広いテーマも立派な会議テーマになります。
多職種会議として認められるための条件
- 医療・介護・福祉に関わる複数職種が関与
- 地域住民または具体的な対象者を想定した議論がある
- 議事録や支援計画など、アウトプットが残る
地域活性化をテーマとした会議の事例
- 「フレイル予防教室を地域でどう立ち上げるか?」
- 「災害時に薬局が果たす役割と他職種との連携」
- 「健康フェアの共催と医療職の役割分担」
- 「子ども食堂と服薬支援の接点づくり」

注意点:抽象的すぎるテーマはNGになることも
ただし、「地域活性化をなんとなく語るだけ」のような抽象的な内容では、多職種“連携”や“支援方針の共有”とはみなされにくくなります。
「誰に対して・どんな支援を・どう行うか」が議論されていれば、十分に評価対象となる会議になります。

実はそういうテーマこそ、他職種を巻き込むチャンスになるかも♪
会議当日はどう進める?記録はどう残す?
いよいよ会議当日。
準備した内容をスムーズに進行し、記録に残すことが重要です。
ここでは、現場でそのまま使える具体的な進行方法と記録フォーマットをご紹介します。
会議進行の5つのステップ
- ① 開会のあいさつ:「本日はお集まりいただきありがとうございます。○○さんの支援について意見交換をお願い致します」など
- ② 状況説明:薬剤師が中心となって現状を簡潔に報告(服薬状況・困っている点など)
- ③ 各職種の意見交換:看護・介護・リハ・医師などから順番にコメント
- ④ 対応方針の確認:今後の支援方針や担当者の役割を整理
- ⑤ 閉会と今後の連絡方法の確認:メール・電話・LINE WORKSなど

記録はA4一枚でOK!フォーマット例
記録は簡潔かつ再利用できる形式で残しておくと便利です。以下はテンプレートの例です:
| 項目 | 記入内容 |
|---|---|
| 開催日・時間 | 2025年○月○日 14:00〜14:45 |
| 会議方法 | Zoom/対面(○○薬局会議室) |
| 対象者氏名(匿名可) | Aさん(85歳、独居) |
| 主な議題 | 服薬アドヒアランスの低下と見守り支援の導入 |
| 参加職種 | 薬剤師・訪問看護師・ケアマネ・リハ職 |
| 決定事項 | 服薬カレンダー導入・週1訪問時の服薬チェック実施 |
| 担当分担 | 薬剤師→薬カレ準備、看護→服薬確認、ケアマネ→家族連絡 |
このような記録は、施設内の共有フォルダやGoogleドライブ、Dropboxなどに保存すると便利です。
後日共有とフィードバックも大切!
会議で決まった内容は、他のスタッフやご家族にも「見える形」で伝えることが重要です。
後日メールでの報告や、必要に応じてLINE WORKSで概要共有も行いましょう。

薬剤師がすべて企画しなくていい!負担を減らすコツは?
多職種会議を企画するにあたって、「全部自分でやらないといけない…」と思っていませんか?
大丈夫!実は薬剤師は“きっかけ”を作るだけでも十分に価値があります。
負担を減らすための3つの工夫
- ① ケアマネや看護師に「一緒に企画しませんか?」と提案
– ケアマネは会議を定期的に開く必要があるため、喜ばれることが多いです - ② 会議フォーマットを共有して、進行役を他職種に振る
– 進行を依頼し、自分は薬剤師としての発言と記録だけに集中 - ③ LINE WORKSやメールで“オンライン事前会議”
– 対面が難しければチャットベースでも“実質的な会議”とみなされるケースも

“共催スタイル”でも加算・評価の対象になります!
たとえ薬剤師が主催でなくても、薬剤師が企画に関与し、発言・記録・報告に関われば、それは評価される立派な実績です。
「薬局で多職種会議を1件でも増やす」ために、“巻き込む力”こそが一番大切です。

周囲に頼って、それも“連携”の第一歩だね!
【実践編】薬剤師が関与した多職種会議の事例
ここでは、実際に薬局薬剤師が関わった多職種会議の事例を3つ紹介します。
“この程度でもOKなんだ!”と感じられる規模感と内容を意識して、現場での応用に役立ててください。
事例①:認知症独居高齢者の服薬支援
- 対象者:87歳女性、独居、軽度認知症
- 課題:処方薬が服薬できず溜まってしまう。本人は服薬拒否もある。
- 参加者:薬剤師・訪問看護師・ケアマネージャー
- 対応:薬剤師が「週2回訪問し服薬サポート」を提案。服薬カレンダー導入。
- 結果:2週間後には残薬がほぼ解消。患者の拒否も減少。
事例②:多剤併用によるふらつきの改善
- 対象者:80歳男性、在宅酸素療法中
- 課題:ふらつきと転倒が頻発。薬剤の副作用が疑われた。
- 参加者:薬剤師・主治医・看護師
- 対応:薬剤師が処方薬8種のうち3種を医師へ減薬提案。
- 結果:転倒が減少し、訪問リハビリ再開。
事例③:終末期の疼痛緩和と意思共有
- 対象者:79歳女性、がん末期、在宅看取り希望
- 課題:家族がモルヒネ導入に不安を抱いていた
- 参加者:薬剤師・主治医・訪問看護師・ケアマネ
- 対応:薬剤師がモルヒネの作用・副作用・使い方を丁寧に説明
- 結果:家族の理解が得られ、疼痛緩和が適切に行われた

まとめ
多職種会議を薬剤師が企画・実践することは、地域支援体制加算の取得だけでなく、患者の生活の質を守る連携のカギとなります。
最初は小さな一歩から始めてOKです。
- 2〜3人の簡単な相談形式でも立派な多職種会議
- 医師が不在でも評価対象になる
- 主催は薬剤師でも問題なし!共催・巻き込み型で効率よく
- 会議テーマは日々の業務の中から見つけよう
- 記録と報告で「連携の証拠」を残そう
“動いた薬剤師から地域連携が始まる”。
まずは一例でも実施して、経験を積んでいきましょう!

「ちょっと話してみませんか?」が地域連携のはじまりだよ♪
A4一枚程度の議事録で十分です。「日時・参加者・議題・決定内容」を簡潔に記載すればOKです。
よくある質問
Q1. 医師がいない会議でも評価されますか?
はい、評価されます。重要なのは「異なる職種が連携して患者支援を話し合ったかどうか」です。医師の参加は必須ではなく、薬剤師・看護師・ケアマネージャーなどで構成された会議も立派な多職種会議として評価されます。
Q2. オンライン会議も加算対象になりますか?
はい、ZoomやLINE WORKSなどを使用したオンライン会議も、記録がきちんと残っていれば評価対象になります。特に時間調整や移動の手間を省けるため、実施しやすく、現場でも推奨されています。
Q3. 記録はどのくらい残すべき?
A4用紙1枚程度の記録で十分です。「開催日」「参加者」「議題」「決定内容」などを簡潔にまとめることで、施設内での共有・評価・報告に活用できます。
Q4. どんなテーマが評価されやすいですか?
評価されやすいテーマは、「服薬管理の見直し」「認知症支援」「終末期ケアの調整」「医療と介護の連携構築」など、患者の生活・医療・介護の複合課題に関わる内容です。
Q5. 会議を実施したことはどう報告すればいいですか?
施設内の報告書や実施記録台帳に記録するだけでなく、必要に応じて加算要件の届出書類や自己点検表に反映させます。記録を共有フォルダやクラウドに保存しておくと便利です。
参考文献
- 令和6年度 診療報酬改定概要【調剤】(地域支援体制加算含む)‑ 厚生労働省
- 地域支援体制加算の施設基準と届出方法‑ 管理薬剤師.com
- 2024年度改定後の地域支援体制加算の算定要件解説‑ M3 Pharmacist
- 地域支援体制加算の区分と施設基準一覧表‑ DGS‑on‑line
- 調剤報酬等に係る届出のはは((NPhA調査)‑ 日本保険薬局協会

なんだか最近元気ないね

うん、実は転職を考えてるんだ。
今の仕事にはちょっとマンネリを感じててさ。やっぱり新しい挑戦がしたいなと思って。

それは驚いた。次はどんなところにしようか考えてるの?

まだはっきり決めてないけど、少しリサーチを始めてるところなんだ!

それならまずはここの求人・転職サイトに登録してみるといいよ。求人情報の内容が濃くておすすめなんだ。
職場の雰囲気や経営状況、残業などの忙しさなど、 デメリットな情報であっても、現場の生の声を教えてくれるんだ。

こういうのって必ず転職しなくちゃいけないのかな?

今すぐ転職したい人に限らず、ちょっと考え中の人でも良いみたいだよ。
丁寧なカウンセリングをしてくれるので、色々と相談にのってくれると思うよ。

そうなんだ。
それなら登録だけでもしてみようかな。

迷ったら、2〜3社に登録して比較してみるのがコツだよ!それぞれにしかない強みを活かして、理想の職場を見つけようね!
薬剤師の転職を考える際、信頼できる転職サイトの選定は非常に重要です。
ここでは、「ファーマキャリア」「ヤクジョブ」「ファルマスタッフ」「お仕事ラボ」「ファゲット」の5つの転職サイトについて、それぞれの特徴や強みを比較し、どのような方におすすめかを詳しく解説します。
ファーマキャリアの特徴と強みは?
オーダーメイド求人と手厚いサポート
ファーマキャリアは、薬剤師専門の転職支援サービスであり、特にオーダーメイド求人の提供に定評があります。
経験豊富なコンサルタントが、求職者一人ひとりの希望やキャリアプランに合わせた求人を提案し、転職活動をサポートします。
また、コンサルタントが担当する求職者の数を限定しているため、きめ細やかな対応が可能です。
これにより、転職後のミスマッチを防ぎ、満足度の高い転職を実現しています。
ただし、地方の求人が少ないとの声もあり、都市部での転職を希望する方に特に適しています。

ヤクジョブの特徴と強みは?
全国対応と豊富な求人
ヤクジョブは、全国の求人を取り扱っており、地方在住の方にも利用しやすい転職サイトです。
求人数が豊富で、正社員、パート、派遣など多様な雇用形態に対応しています。
また、コンサルタントのサポートが丁寧で、面接対策や履歴書の添削など、転職活動全般をサポートしてくれます。
特に、ライフスタイルに合わせた求人提案が得意で、子育て中の方やワークライフバランスを重視する方に適しています。
一方で、連絡がしつこいと感じる方や、コンサルタントの質にばらつきがあるとの声もあります。

ファルマスタッフの特徴と強みは?
高年収求人と全国展開
ファルマスタッフは、調剤薬局の高年収求人を多数保有しており、年収アップを目指す方におすすめの転職サイトです。
また、全国に12カ所の支店を展開しており、地方での転職にも対応しています。
コンサルタントが企業に足を運び、職場の情報を収集しているため、求人票だけでは分からない情報を提供してくれます。
さらに、面接に同行してくれるなど、手厚いサポートが特徴です。
ただし、企業薬剤師やドラッグストアの求人が少ないとの声もあり、調剤薬局での転職を希望する方に特に適しています。

お仕事ラボの特徴と強みは?
ワークライフバランス重視と高い定着率
お仕事ラボは、ワークライフバランスを重視した求人紹介に定評があり、年間休日120日以上や残業ほぼなしなど、働きやすい環境の求人を多数取り扱っています。
また、転職後の定着率が95.6%と高く、入社後のフォロー体制も充実しています。
Eラーニングサービス「MPラーニング」の提供や、薬剤師賠償責任保険への無料加入など、派遣社員へのサポートも手厚いです。
ただし、派遣の求人数が少ないとの声もあり、正社員やパートでの転職を希望する方に特に適しています。

ファゲットの特徴と強みは?
利用者目線の対応と高いレスポンス
ファゲットは、薬剤師専門の転職サイトとして23年以上の実績を持ち、利用者目線の対応と高いレスポンスが評判です。
転職者の立場に立った親身な対応を心がけており、条件や希望に合う非公開求人情報を迅速に提供してくれます。
また、オファーシステムを導入しており、匿名で登録しておくだけで、採用側からのオファーメールを受け取ることが可能です。
これにより、今すぐ転職を考えていない方でも、年収アップにつながるチャンスがあります。
ただし、地方都市での求人数が少ないとの口コミもあり、都市部での転職を希望する方に特に適しています。

まとめ
各転職サイトの特徴を比較すると、以下のようになります。自分のライフスタイルやキャリアプランに合ったサイトを選ぶことが、満足のいく転職につながります。
| 転職サイト | 強み | おすすめの方 |
|---|---|---|
| ファーマキャリア | オーダーメイド求人、手厚いサポート | 都市部での転職を希望する方 |
| ヤクジョブ | 全国対応、豊富な求人、柔軟な雇用形態 | 地方在住で多様な働き方を希望する方 |
| ファルマスタッフ | 高年収求人、全国展開、面接同行などのサポート | 調剤薬局での転職を希望する方 |
| お仕事ラボ | ワークライフバランス重視、高定着率 | 働きやすさを重視する方 |
| ファゲット | 利用者目線の対応、匿名オファー制度 | 都市部で条件交渉も重視したい方 |

よくある質問/Q&A
Q1. 複数の転職サイトに登録しても大丈夫ですか?
A. はい、複数の転職サイトに登録することで、より多くの求人情報を得ることができ、自分に合った職場を見つけやすくなります。
Q2. 転職サイトの利用は無料ですか?
A. はい、今回ご紹介した転職サイトはすべて無料で利用できます。 登録や相談、求人紹介などのサービスに料金はかかりません。
Q3. 転職サイトのサポート内容はどのようなものがありますか?
A. 各転職サイトでは、求人紹介、履歴書や職務経歴書の添削、面接対策、条件交渉、入職後のフォローなど、転職活動全般をサポートしてくれます。



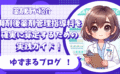
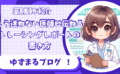
コメント