


薬局の現場で処方箋を受け取ったとき、内服薬が何剤なのかを瞬時に判断する力は、調剤報酬の正確な算定に直結します。
しかし、「1剤=1種類の薬」と早合点してしまうと、算定ミスや過剰・過少請求につながることも…。
この記事では、調剤報酬における「1剤」の定義と考え方を、最新の情報と具体例をもとにわかりやすく解説します。
「服用時点が同じ=1剤」という原則を軸に、内服薬・頓服薬・外用薬のそれぞれの扱い方や、算定の実務ポイントもあわせて紹介していきます。
「1剤」と「1調剤」の違いとは?
調剤報酬の算定においては、「1剤」と「1調剤」という用語が頻繁に登場しますが、それぞれの定義と使い分けをしっかり理解しておくことが重要です。
| 項目 | 1剤 | 1調剤 |
|---|---|---|
| 主な使用場面 | 内服薬の調剤料算定 | 内服・頓服・外用すべての調剤料算定 |
| 定義 | 服用時点が同じ薬剤群をまとめた単位 | 服用時点が同じ かつ 投与日数も同じ薬剤群を1単位とする |
| カウント方法 | 例:朝食後に3種類出ていれば1剤 | 例:Rp番号が異なれば、それぞれ1調剤 |
| 算定の上限 | 原則3剤まで | 制限なし(処方単位でカウント) |
重要なポイントとして、「1剤」は服薬時点でまとめるのに対し、「1調剤」は薬の種類・服用時点・日数をすべて考慮して分けられるという点です。
したがって、「1剤」=同じ時間にまとめて服用するセット、「1調剤」=調剤行為の単位(処方単位)と理解すると、実務での判断がしやすくなります。
内服薬・頓服薬・外用薬での「1剤」「1調剤」のカウント方法は?
内服薬の場合
内服薬は「服用時点」に基づいて1剤をカウントします。
- 朝食後:アムロジピン・バイアスピリン → 1剤
- 夕食後:アトルバスタチン → 1剤
この場合、「2剤」として算定可能です。さらに、1回の受付で最大3剤までが調剤料の算定対象となります。
頓服薬の場合
頓服薬は原則として1つの処方(Rp)単位=1調剤です。
- Rp.1:カロナール頓服(発熱時) → 1調剤
- Rp.2:レボセチリジン(蕁麻疹時) → 1調剤
頓服薬は服用時点や薬効の違いにかかわらず、Rpが分かれていればそれぞれ「1調剤」となります。
外用薬の場合
外用薬(貼付剤・軟膏・点眼薬など)も、原則として処方ごとに1調剤とします。
- Rp.1:モーラステープ → 1調剤
- Rp.2:リンデロンVG軟膏 → 1調剤
点眼薬で2種類処方された場合も、それぞれ別Rpならば「2調剤」になります。
注意すべきポイント
調剤料の点数に直結するため、服用時点と処方単位の把握が必須です。
特に内服薬では、剤数の取り違えで点数が変わるため、確認の徹底が求められます。
症例で学ぶ!「1剤」と「1調剤」のカウント練習
以下の処方例をもとに、「1剤」と「1調剤」がそれぞれ何単位になるか考えてみましょう。
症例で学ぶ!「1剤」と「1調剤」のカウント練習
以下の処方例をもとに、「1剤」と「1調剤」がそれぞれ何単位になるか考えてみましょう。
【症例1】高血圧・脂質異常症の患者
Rp.
アムロジピン5mg 朝食後
バルサルタン80mg 朝食後
Rp
ロスバスタチン5mg 夕食後
正解は B:2剤・2調剤
朝食後のアムロジピンとバルサルタンは服用時点が同じため1剤。夕食後のロスバスタチンは別の服用時点なので別剤。Rpは2つで日数も同じなので2調剤です。
【症例2】感冒時の処方
Rp.1 カロナール錠200mg 発熱時(頓服)
Rp.2 レボセチリジン5mg 就寝前 5日分
正解は B:1剤・2調剤
レボセチリジンは内服薬で就寝前なので1剤。頓服薬は1剤に含まれません。Rpが異なるため調剤料は2調剤です。
【症例3】湿布と塗り薬が処方された場合
Rp.1 モーラステープ20mg 1日1回 14枚
Rp.2 ロコイド軟膏0.1% 1日2回 5g
正解は B:0剤・2調剤
外用薬は1剤のカウント対象外ですが、Rpが異なるため調剤料は2調剤として算定されます。
薬局として気をつけるべきポイントは?
「1剤」と「1調剤」の取り違えは、調剤報酬の算定ミスにつながり、監査や返戻の対象になる可能性があります。
以下のポイントを日常業務で意識することが重要です。
① 服用時点に注目して1剤を数える
特に内服薬の場合、「朝・昼・夕・就寝前・毎食後・食間」などの具体的な服用時点が記載されているかを必ず確認しましょう。同じ薬効でも服用時点が異なれば別剤になります。
② 頓服・外用薬はRp単位で数える
頓服薬・外用薬は「服用(使用)時点」ではなく、処方(Rp)の単位ごとに1調剤として数えます。指示が異なる場合や、日数が分かれている場合にも注意しましょう。
③ 処方せんの記載が不明確なときは疑義照会も
「毎食後」や「1日2回」のようにざっくりした表現だけで服用時点が明示されていない処方せんもあります。この場合、算定できる剤数が変わる可能性があるため、必要に応じて疑義照会を行うことが重要です。
④ 電子薬歴やレセコンでの自動カウントを過信しない
調剤システムに搭載された自動カウント機能は便利ですが、最終的には薬剤師の目で確認し、ルールに即した判断を行うべきです。
⑤ 点数改定・通知は逐次チェック
調剤報酬の点数や算定要件は改定されることがあります。厚生労働省の通知や地方厚生局の通達を定期的に確認しましょう。

まとめ
この記事では、調剤報酬の現場で混乱しがちな「1剤」と「1調剤」の違いについて、定義から数え方、実務での注意点まで詳しく解説しました。
- 1剤=服用時点が同じ内服薬のグループ
- 1調剤=Rp(処方)単位でのカウント(内服・頓服・外用問わず)
- 内服薬は最大3剤まで算定できるが、服用時点がポイント
- 頓服・外用薬はRpごとに調剤料が加算される
- 記載が不明瞭な場合は、疑義照会で確認
算定ミスは監査・返戻の原因になりやすいため、薬局全体でのルール共有と定期的な見直しが求められます。
この記事を参考に、「1剤」と「1調剤」の正確な理解を深め、日々の業務に自信を持って取り組んでいきましょう!

選択式クイズで復習しよう!
Q1. 以下の内服薬は何剤とカウントされる?
・アムロジピン5mg 朝食後
・バルサルタン80mg 朝食後
・ロスバスタチン5mg 夕食後
正解は B:2剤
アムロジピンとバルサルタンは「朝食後」で服用時点が同じなので1剤、ロスバスタチンは「夕食後」なので別の1剤。合計2剤です。
Q2. 次のうち「1調剤」として正しいカウント方法はどれ?
Rp.1 カロナール錠(頓服)
Rp.2 ロキソニンテープ(外用)
正解は B:2調剤
頓服薬も外用薬もRpが別れていれば、それぞれで1調剤としてカウントします。剤形や薬効ではなく、Rp単位で見ます。
Q3. 「1剤」のカウントにおいて最も重視すべきポイントは?
正解は C:服用時点
「1剤」としてカウントする際は、薬の種類や剤形よりも、服用時点が同じかどうかが最重要の判断基準になります。
Q4. 以下のような処方内容の場合、「1剤」「1調剤」はどうカウントする?
Rp.1
・メトホルミン250mg 朝夕食後(分2)
・エンパグリフロジン10mg 朝食後(分1)
・ロサルタン50mg 朝食後(分1)
Rp.2
・カロナール錠200mg 発熱時(頓服)
正解は B:2剤・2調剤
【1剤】朝食後にエンパグリフロジン・ロサルタン・メトホルミン(朝分)で1剤、夕食後のメトホルミン(夕分)で1剤 → 合計2剤。
【1調剤】Rp.1(内服)+ Rp.2(頓服)は別Rpなので → 合計2調剤。
ポイント:「分2」の場合でも服用時点が異なれば別剤とカウントします。また、頓服薬は1剤には含まず、調剤料として別カウントします。
よくある質問(FAQ)
Q. 服用時点が「朝・夕」の薬は何剤として数えますか?
A. 「朝・夕食後」はそれぞれ別の服用時点と見なされるため、同じ薬剤でも2剤に分けてカウントします。1日2回の服用でも「分2」の記載だけでは1剤にはなりません。
Q. 同じ薬が2種類の剤形で処方された場合は?(例:錠剤+ドライシロップ)
A. 同じ有効成分でも服用時点が同じなら1剤にまとめられます。剤形が異なっても、タイミングが一緒なら問題ありません。
Q. Rpが1つにまとまっているが、服用時点が異なる薬が含まれるときは?
A. 処方が1Rpでも、服用時点ごとに1剤ずつカウントします。Rp単位と1剤のカウントは別の基準です。
Q. 調剤システムの自動カウント結果が怪しいときはどうする?
A. 自動判定は便利ですが最終判断は薬剤師の確認が必要です。不明点があれば疑義照会も視野に入れましょう。
Q. 点数算定ミスが見つか…、ったら、レセプト提出後でも修正可能ですか?
A. 地方厚生局のルールや保険者によりますが、再請求や訂正レセプトの提出が必要になる場合があります。発見次第、速やかに対応しましょう。
参考文献
- 平成30年度 診療報酬改定調剤報酬の改定について(厚生労働省)
- 調剤料の1剤とは?分かりやすく解説|kakari for Pharmacy
- 「1調剤」と「1剤」の違いとは?|株式会社医療経営研究所
- 調剤報酬の「1剤」とは?服用時点で決まる定義を解説|note
- 【調剤報酬2024】薬剤調製料・調剤料の算定ポイントまとめ|社会保険研究所
- 管理薬剤師.com








\忙しい薬剤師でもOK!最短で合格を目指すならココ/
【呼吸療養認定士】吸入指導のエキスパートへ!
「吸入薬、うまく使えてないな…」という患者さん、多くないですか?
この資格があれば、吸入デバイス指導から生活指導まで、医師に一目置かれる存在に。
✅ 呼吸器疾患への薬物療法が体系的に理解できる
✅ COPDや喘息の服薬アドヒアランスに貢献
✅ 地域包括ケアでの活躍チャンス拡大!
【透析技術認定士】電解質・水分管理の知識が武器になる!
透析患者の処方、なんとなくで扱っていませんか?
この資格で「透析処方が読める薬剤師」になれます。
✅ 血液・腹膜透析の薬学的視点がしっかり学べる
✅ 高カリウム血症やP管理などのアセスメント力がアップ
✅ チーム医療の中で活躍の場が広がる!
【認知症ケア認定士】「ただの服薬指導」からの脱却!
認知症の方との会話に困ること、ありませんか?
この資格で「認知症に寄り添える薬剤師」になれます。
✅ BPSD(行動心理症状)への対応知識も学べる
✅ 在宅・施設での多職種連携がスムーズに
✅ ケアマネや家族からの信頼も高まる!
【糖尿病療養認定士】薬だけじゃない、生活まで支える力!
HbA1cばかり見ていませんか?
この資格があれば、「生活までアドバイスできる薬剤師」に。
✅ 食事・運動・インスリンまで包括的に学べる
✅ SMBG・インスリン注射の技術支援にも対応
✅ 外来・薬局・在宅、どの現場でも活躍できる!
悩んでいる時間がもったいない。今日から一歩踏み出そう!









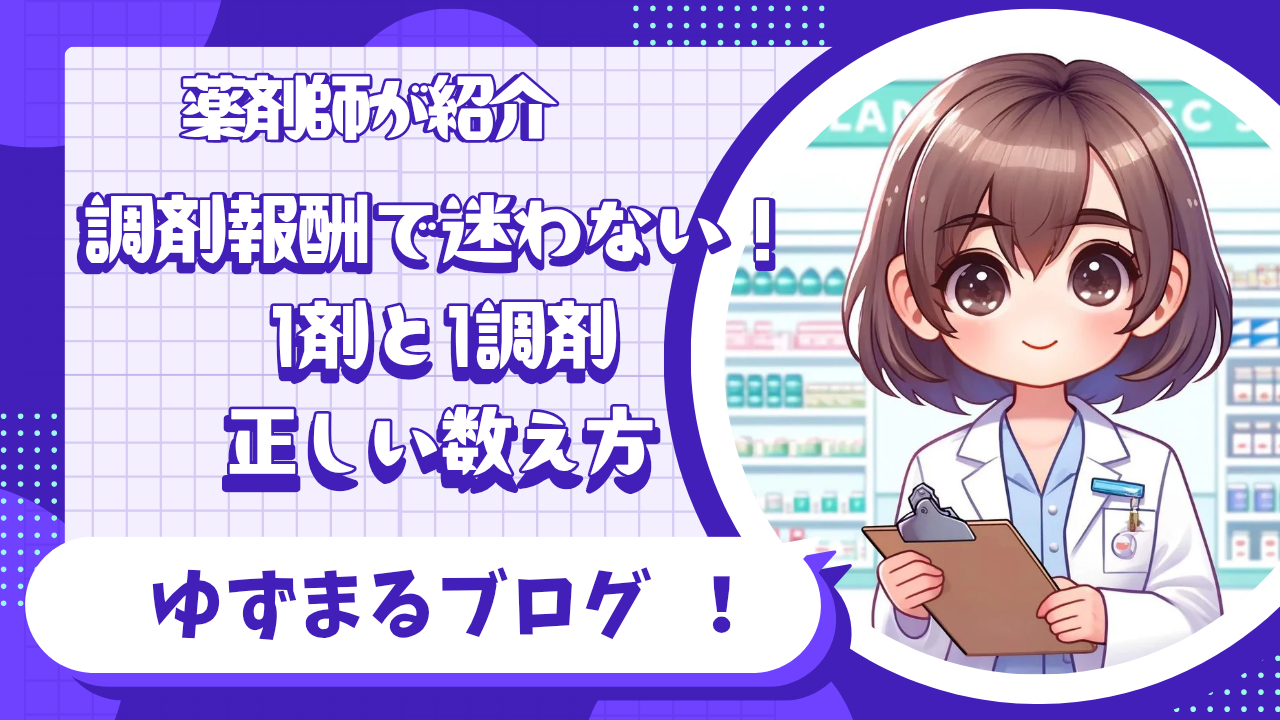

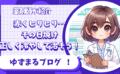
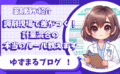
コメント