

この記事では、薬剤師の視点から「なぜ冷房をつけていても熱中症になるのか?」を科学的に解説し、家庭や薬局でできる実践的な対策をまとめます。
さらに、具体的な症例やケーススタディも交えて、読者がすぐに役立てられる情報を提供します。
夏を安全に快適に過ごすために、ぜひ最後までご覧ください。
- 冷房中でも熱中症になるのはなぜ?体の仕組みから見直す?
- 湿度とWBGT(暑さ指数)をどう見れば安全管理できる?
- 室内でどんなときに起きやすい?具体的なシーンは?
- 誰が特にリスク?服用中の薬は関係する?
- エアコンの設定・使い方はどう最適化する?
- 水分・電解質はどう摂ると安全?
- 症状が出たらどうする?家庭での初期対応は?
- 薬局薬剤師はどう支援する?在宅・外来での実践は?
- ケースで学ぶ:どんな工夫が効いた?
- 理解度チェック:正しいのはどれ?
- よくある質問(Q&A)は?
- 部屋別にどう改善する?チェックリストは?
- おすすめの道具どれを選ぶ?
- セルフチェックリストで今日から実行できる?
- まとめ
- 参考文献
- 薬剤師向け転職サービスの比較と特徴まとめ
冷房中でも熱中症になるのはなぜ?体の仕組みから見直す?
人の体は、発汗(気化熱)と皮膚血流で熱を放散し、深部体温を約37℃に保っています。
しかし、湿度が高い・風が弱い・日射や機器からの輻射熱が強いと、汗が蒸発しにくくなり、熱が体内にこもります。
これが冷房中でも熱中症が起きる大きな理由です。
特に日本の夏は湿度が高く、室温が下がっても汗の蒸発が追いつかず、体温がじわじわ上がる“隠れオーバーヒート”が起こりやすくなります。
さらに、高齢者・乳幼児・基礎疾患を持つ方・一部の薬を服用中の方は体温調節がうまく働きにくく、室内でもリスクが高くなります。
夜間の「寝苦しさ・こむら返り・頭痛・だるさ」は、軽い脱水や熱疲労のサインです。
| 室内環境の例 | 体に起きること | リスク |
|---|---|---|
| 設定温度28℃・湿度75%・無風 | 汗が蒸発せず熱がこもる | 高 |
| 設定温度26℃・湿度65%・直射日光あり | 窓からの輻射熱で体感温度上昇 | 中~高 |
| 設定温度27℃・湿度50%・サーキュレーター併用 | 汗が蒸発しやすい | 低~中 |

湿度とWBGT(暑さ指数)をどう見れば安全管理できる?
WBGT(暑さ指数)は、湿度・輻射熱・気温を総合した指標です。屋内でも湿度と周辺の熱で上がるため、「エアコン=安全」ではありません。
目安として、WBGT 28 以上は厳重警戒で、熱中症の救急搬送が増えます。
室内の温湿度計に加えて、WBGT計や環境省サイトの地域情報も参考にしましょう。
| WBGT区分 | 目安 | リスク | 室内の目安対策 |
|---|---|---|---|
| 21未満 | 注意 | 低 | 通常の生活。適宜換気・水分。 |
| 21~25 | 警戒 | 中 | 運動や家事の強度を調整。水分補給。 |
| 25~28 | 厳重警戒 | 中~高 | 除湿・断熱・扇風機/サーキュレーター併用。 |
| 28超 | 危険 | 高 | 無理な活動を避け、冷房+除湿+休憩。 |

室内でどんなときに起きやすい?具体的なシーンは?
- 就寝中:エアコンのタイマーオフ後に室温・湿度が上がり、寝汗+脱水→明け方のこむら返りや頭痛。
- 在宅ワーク:PC・照明・機器の発熱(輻射熱)、換気不足で湿度上昇。
- 風呂上がり・洗濯物の室内干し:一時的に湿度80%超まで上がることも。
- 南向きの部屋・大型窓:午後の日射で体感温度アップ。遮光が弱いと危険。
- 高齢者の一人暮らし:寒暖感覚の低下、節電意識、「のどが渇かない」による水分不足。
これらはすべて、冷房をつけていても熱中症が起きる典型です。
除湿・送風・遮光をセットにしましょう。

誰が特にリスク?服用中の薬は関係する?
ハイリスク群は、65歳以上・乳幼児・妊娠中・持病(心不全、腎疾患、糖尿病など)・過去に熱中症歴がある人。さらに、以下の薬は体温調節や水分バランスに影響することがあります。
- 抗コリン作用薬(一部の抗ヒスタミン薬、抗精神病薬、パーキンソン病薬など):発汗低下
- β遮断薬:皮膚血流増加が抑えられ、放熱が低下
- 利尿薬:脱水・電解質異常
- SGLT2阻害薬:浸透圧利尿により体液量が減少しやすい
- 睡眠薬・鎮静薬:口渇や水分摂取の遅れ
処方薬・市販薬ともに、夏の服薬指導では上記のポイントを確認し、水分・電解質管理の計画を一緒に立てましょう。
既往や腎機能・心機能に応じて、飲水量や塩分量は個別化が必要です。

エアコンの設定・使い方はどう最適化する?
設定温度と湿度はどう決める?
- 目安:室温26~28℃、湿度40~60%。湿度が高いほど危険なので、迷ったら除湿(ドライ)を優先。
- 寝室は弱冷房+除湿+連続運転で、タイマー切りは避けると安定。
- 在宅ワークは、PC発熱を見越して風量自動・風向スイングに。
送風と気流をどう作る?
- サーキュレーター/扇風機をエアコン対角に置いて空気を回す。
- 直接身体に冷風を当てず、天井や壁に沿わせるイメージで。
- 換気は短時間・強制換気で湿気を逃がす。
日射・輻射熱をどう抑える?
- 遮光カーテン・ブラインド・すだれで窓面をカット。
- 窓ガラスに遮熱フィルムを検討。
- 観葉植物やバルコニーの緑のカーテンも有効。
メンテナンスは何をする?
- シーズン前に試運転。冷えない・異音・エラー表示は点検。
- フィルター清掃を2週間に1度目安で。
- 古い機種・能力不足は買い替えを検討(畳数表示を確認)。
ポイント: 「28℃」は万能の安全温度ではありません。湿度・輻射熱・風を合わせて最適化することが重要です。

水分・電解質はどう摂ると安全?
喉の渇きはあてにならないことがあります。尿の色(淡いレモン色)を目安に、起床時・入浴前後・就寝前にコップ1杯ずつを基本に。
以下は一般的な目安です(持病がある方は必ず主治医に確認してください)。
| 状況 | 推奨される飲み物 | ポイント |
|---|---|---|
| 日常生活(軽作業) | 水・麦茶 | こまめに少量ずつ。 |
| 大量発汗(運動・屋外作業) | スポーツドリンク | 糖とナトリウムで吸収促進。 |
| 脱水症状の兆候(ふらつき、こむら返り等) | 経口補水液(ORS) | 医療補助飲料。短期間の補給に。 |
- カフェイン・アルコールは利尿で脱水を助長することがあるので注意。
- 心不全・腎疾患・利尿薬内服中は飲水制限の範囲で計画的に。

症状が出たらどうする?家庭での初期対応は?
- 涼しい場所へ移動:エアコンの効いた部屋や日陰へ。
- 衣服をゆるめる:ベルト・ネクタイ・下着の圧迫を外す。
- 冷却:首・わき・鼠径部を保冷剤や冷タオルで冷やす(Active Cooling)。
- 水分・電解質の補給:意識清明なら水・スポーツ飲料・経口補水液を。
- 重症サイン:意識障害・けいれん・体温40℃以上・嘔吐持続は、119番通報+救急要請。
回復後もしばらくは無理をせず、再発防止のために環境とスケジュールを見直しましょう。

薬局薬剤師はどう支援する?在宅・外来での実践は?
患者背景の整理はどうする?
- 年齢・既往歴・腎機能・心機能・糖尿病・認知機能・居住環境(階数・方角・断熱)・独居/同居。
- 服用薬(抗コリン薬・利尿薬・β遮断薬・SGLT2阻害薬・鎮静薬など)。
- 生活パターン(就寝時エアコン、入浴時間、室内干しの有無、在宅ワークの時間)。
指導の具体例は?
- 温湿度計+WBGT計の活用を提案。「数字で可視化」して行動変容へ。
- 就寝時は連続運転、除湿優先、遮光と気流確保。
- 飲水計画(起床時・入浴前後・就寝前に各200mLなど)。
- 薬剤の副作用リスクと受診目安(倦怠感、ふらつき、食欲不振、筋痙攣など)。
おすすめの生活・備えは?
- 温湿度計、WBGT計、経口補水液、保冷剤、サーキュレーター、遮光カーテン。
- 停電時の備え(電池・モバイルバッテリー・保冷バッグ)。
- 独居高齢者には「見守り・声かけ」の仕組みづくり。

ケースで学ぶ:どんな工夫が効いた?
ケース1:独居高齢者で夜間に足がつるのはなぜ?
背景:75歳女性、利尿薬内服中。就寝時はエアコン28℃でタイマー3時間、翌朝こむら返り。
介入:連続運転へ変更、除湿優先、就寝前に200mLの水分+軽い塩分(食事で調整)、足元に薄手のブランケット。
結果:夜間のこむら返りが減少、疲労感も改善。
ケース2:在宅ワークで午後の頭痛が続く?
背景:30代男性、南向きワンルーム。午後だけ頭痛・だるさ。
介入:遮光カーテン導入、サーキュレーターで気流確保、PC周りの発熱源整理、定時の飲水。
結果:午後の不調が軽減、集中力が改善。
ケース3:乳幼児のいる家庭での入浴後のぐずり?
背景:1歳児、入浴後にぐずって寝つきが悪い。
介入:脱衣所に除湿機、入浴後は扇風機で送風、パジャマは吸湿速乾素材。
結果:入眠がスムーズになり、夜間の発汗量も減少。

理解度チェック:正しいのはどれ?
選択肢から答えを選んで、下のボックスで答え合わせ!
問題1:「室温28℃なら湿度関係なく安全である」
- A. そう思う
- B. そうは思わない
答え: B
解説: 温度だけでは不十分で、湿度・輻射熱・風が重要。湿度が高ければ28℃でも危険。
問題2:「扇風機だけでも、室温33℃以上では体温が上がることがある」
- A. そう思う
- B. そうは思わない
答え: A
解説: 高温環境では扇風機の風だけでは熱が逃げず、体温が上昇。冷房や除湿との併用が必要。
問題3:「こむら返りが出たら、経口補水液(ORS)を短期間活用する選択がある」
- A. そう思う
- B. そうは思わない
答え: A
解説: こむら返りや脱水兆候がある場合は、短期間に限って経口補水液を活用。ただし持病がある方は医師に確認を。
よくある質問(Q&A)は?
就寝中、エアコンはタイマーで切ってもいい?
夜間は湿度と室温が上がりやすいため、連続運転がおすすめです。冷えすぎが心配なら、風向を天井に、風量自動、除湿優先に設定しましょう。
除湿(ドライ)と冷房、どちらを優先すべき?
体感の安全性は湿度に左右されます。まずは除湿で湿度60%以下をめざし、必要に応じて冷房を併用します。
経口補水液は毎日飲んでもいい?
経口補水液は短期間・必要時に使う医療補助飲料です。日常は水や麦茶を基本に、発汗が多い日はスポーツドリンクを活用しましょう。腎・心疾患のある方は医療者に相談してください。
冷房が苦手な家族がいるときの妥協案は?
遮光・除湿・気流の3点を整えると、設定温度を上げても快適性が保ちやすくなります。衣服の調整や、冷感寝具も有効です。

部屋別にどう改善する?チェックリストは?
寝室はどう整える?
- 連続運転+除湿:タイマーオフで夜間に暑さが戻るのを防ぐ。
- 冷気の直当てを避ける:風向は天井。サーキュレーターで空気を回す。
- 寝具:吸湿速乾のシーツ、枕カバー。冷感寝具は汗戻りに注意。
- 就寝前のルーティン:入浴後は扇風機で送風→就寝前200mL飲水。
リビング・在宅ワークスペースは?
- 遮光:南西面の窓は遮光カーテンやブラインド、遮熱フィルム。
- 気流設計:エアコンと対角線上にサーキュレーター、背面から壁沿いに送風。
- 発熱源の整理:PC・照明・調理家電の使用時間を分散。
- 水分ステーション:デスクに水・麦茶を常備、30~60分ごとに一口。
キッチン・脱衣所・浴室は?
- 短時間換気+除湿:調理・入浴後は一時的に湿度が急上昇。
- 衣類の室内干し:除湿機の排水タンク容量を確認、満水停止に注意。
- 滑り対策:汗や湯気で床が湿ると転倒リスク。マットで予防。
高齢者・乳幼児のいる家庭の工夫は?
- 声かけ・見守り:独居高齢者には家族・地域で定時連絡。
- 飲み物の見える化:冷蔵庫に見やすく並べ、手の届く位置に常備。
- 衣服:通気性・吸湿性・速乾性を重視。乳幼児は背中にガーゼで汗チェック。
おすすめの道具どれを選ぶ?
薬事法に抵触しない範囲で、安全管理の「見える化」と快適化に役立つアイテムを紹介します(製品名は例、選定はスペック・価格・保証で比較を)。
- 温湿度計:数字で管理。最小/最大記録・アラート機能付きが便利。
- WBGT計:室内外のリスク評価に。アラームで「行動の合図」。
- サーキュレーター:静音・首振り・上下左右可動を重視。
- 除湿機:コンプレッサー式(夏向き)・デシカント式(冬向き)・ハイブリッド式。
- 遮光・遮熱カーテン:等級表示をチェック。窓枠側からの熱侵入をカット。
- 経口補水液/スポーツドリンク:用途に応じて使い分け。ラベル記載の飲み方を遵守。
- 保冷剤・冷感タオル:頸部・腋窩・鼠径部の冷却に備える。
上記はあくまで生活支援用品です。
治療や効果・効能を標榜するものではありません。
持病や妊娠中の方は、事前に医療者へご相談ください。

セルフチェックリストで今日から実行できる?
- □ 温湿度計・WBGT計で数値を把握している
- □ 就寝中は連続運転+除湿でタイマー切りをしていない
- □ 窓の遮光・遮熱をしている(特に南西面)
- □ サーキュレーターで気流を作っている
- □ 入浴・調理・室内干し直後は短時間換気+除湿をしている
- □ 起床時・入浴前後・就寝前に定時の飲水をしている
- □ ハイリスクの家族には声かけ・見守りの仕組みがある

まとめ
- 冷房中でも、湿度・輻射熱・風が整っていないと熱中症は起こる。
- WBGT 28以上は厳重警戒。除湿・遮光・気流をセットで対策。
- ハイリスク群(高齢者・乳幼児・持病・一部の薬)には定時飲水と環境調整を。
- 症状が出たら冷却+補水+休息、重症サインは119番。
- 薬局では、服薬状況と住環境まで含めて伴走支援を。
参考文献
📘『薬局長のためのモンスター社員対応マニュアル』発売のお知らせ
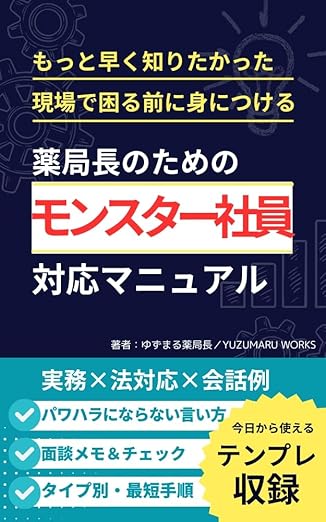
薬局で働いていると、どうしても避けられないのが「人間関係のストレス」。
患者対応、スタッフ教育、シフト調整……。
気がつけば、薬局長がいちばん疲れてしまっている。
そんな現場のリアルな悩みに向き合うために、管理薬剤師としての経験をもとにまとめたのが、この一冊です。






『薬局長のためのモンスター社員対応マニュアル』
― 現場で困る前に身につける 実務 × 法対応 × 会話例 ―
薬局で起こりやすい“モンスター社員”を15タイプに分類し、
それぞれの特徴・対応法・指導会話例を紹介。
パワハラにならない注意方法や、円満退職・法的リスク回避の実務ステップも具体的に解説しています。
- 現場によくある「人のトラブル」15パターンと対応のコツ
- パワハラにならない“安全な指導”の伝え方
- 円満退職を導くための面談・記録・法的ポイント
- 薬局長自身を守るマネジメント思考
薬局で人に悩まないための「実践マニュアル」として、
日々の業務の支えになれば幸いです。
「薬局長が守られれば、薬局全体が守られる」
現場の“声にならない悩み”を形にしました。
📘 書籍情報
-
- 書名:薬局長のためのモンスター社員対応マニュアル
- 著者:ゆずまる薬局長
- 発行:YUZUMARU WORKS
- フォーマット:Kindle電子書籍
- シリーズ:薬局マネジメント・シリーズ Vol.2
📕 シリーズ第1弾はこちら
👉 『薬局長になったら最初に読む本』
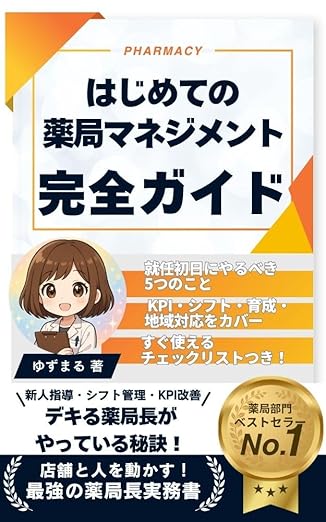






薬剤師向け転職サービスの比較と特徴まとめ


今日は、特徴をわかりやすく整理しつつ、読んでくださる方が自分の働き方を見つめ直しやすいようにまとめていきましょう。
働く中で、ふと立ち止まる瞬間は誰にでもあります
薬剤師として日々働いていると、忙しさの中で気持ちに余裕が少なくなり、
「最近ちょっと疲れているかも…」と感じる瞬間が出てくることがあります。
- 店舗からの連絡に、少し身構えてしまう
- 休憩中も頭の中が業務のことでいっぱいになっている
- 気づけば仕事中心の生活になっている
こうした感覚は、必ずしも「今の職場が嫌い」というわけではなく、
「これからの働き方を考えてもよいタイミングかもしれない」というサインであることもあります。
無理に変える必要はありませんが、少し気持ちが揺れたときに情報を整理しておくと、
自分に合った選択肢を考えるきっかけになることがあります。
薬剤師向け転職サービスの比較表
ここでは、薬剤師向けの主な転職サービスについて、それぞれの特徴を簡潔に整理しました。
各サービスの特徴(概要)
ここからは、上記のサービスごとに特徴をもう少しだけ詳しく整理していきます。ご自身の希望と照らし合わせる際の参考にしてください。
・薬剤師向けの転職支援サービスとして、調剤薬局やドラッグストアなどの求人を扱っています。
・面談を通じて、これまでの経験や今後の希望を整理しながら話ができる点が特徴です。
・「まずは話を聞いてみたい」「自分の考えを整理したい」という方にとって、利用しやすいスタイルと言えます。
・全国の薬局・病院・ドラッグストアなど、幅広い求人を取り扱っています。
・エリアごとの求人状況を比較しやすく、通勤圏や希望地域に合わせて探したいときに役立ちます。
・「家から通いやすい範囲で、いくつか選択肢を見比べたい」という方に向いているサービスです。
・調剤薬局の求人を多く扱い、条件の調整や個別相談に力を入れているスタイルです。
・勤務時間、休日日数、年収など、具体的な条件について相談しながら進めたい人に利用されています。
・「働き方や条件面にしっかりこだわりたい」方が、検討の材料として使いやすいサービスです。
・調剤系の求人を取り扱う転職支援サービスです。
・職場の雰囲気や体制など、求人票だけではわかりにくい情報を把握している場合があります。
・「長く働けそうな職場かどうか、雰囲気も含めて知りたい」という方が検討しやすいサービスです。
・薬剤師に特化した職業紹介サービスで、調剤薬局・病院・ドラッグストアなど幅広い求人を扱っています。
・公開されていない求人(非公開求人)を扱っていることもあり、選択肢を広げたい場面で役立ちます。
・「いろいろな可能性を見比べてから考えたい」という方に合いやすいサービスです。
・調剤薬局を中心に薬剤師向け求人を取り扱うサービスです。
・研修やフォロー体制など、就業後を見据えたサポートにも取り組んでいる点が特徴です。
・「現場でのスキルや知識も高めながら働きたい」という方が検討しやすいサービスです。
気持ちが揺れるときは、自分を見つめ直すきっかけになります
働き方について「このままでいいのかな」と考える瞬間は、誰にでも訪れます。
それは決して悪いことではなく、自分の今とこれからを整理するための大切なサインになることもあります。
転職サービスの利用は、何かをすぐに決めるためだけではなく、
「今の働き方」と「他の選択肢」を比較しながら考えるための手段として活用することもできます。
情報を知っておくだけでも、
「いざというときに動ける」という安心感につながる場合があります。


「転職するかどうかを決める前に、まずは情報を知っておくだけでも十分ですよ」ってお伝えしたいです。
自分に合う働き方を考える材料が増えるだけでも、少し気持ちがラクになることがありますよね。
無理に何かを変える必要はありませんが、
「自分にはどんな可能性があるのか」を知っておくことは、将来の安心につながることがあります。
気になるサービスがあれば、詳細を確認しながら、ご自身のペースで検討してみてください。

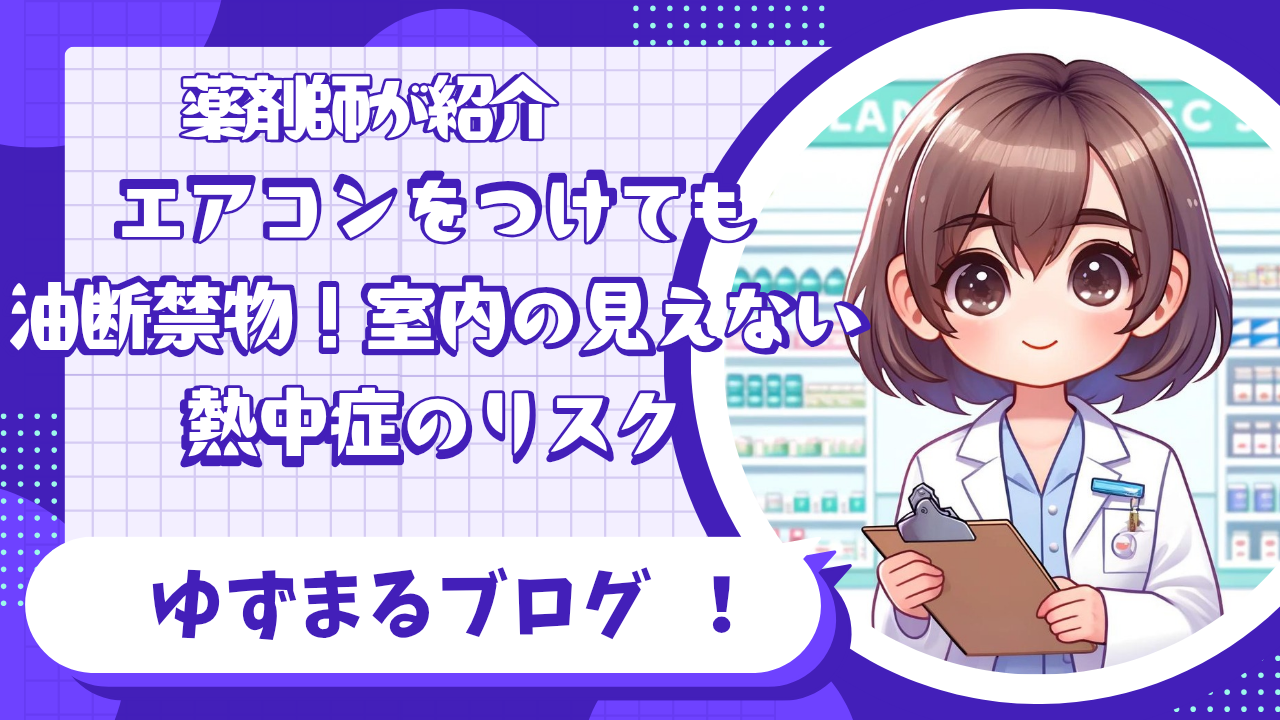

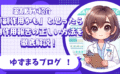
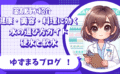
コメント