


近年、薬剤師の業務評価のなかでも「服用薬剤調整支援料」は、多剤併用の是正に関わる対人業務として注目されています。
特に超高齢社会を迎えた日本においては、重複投薬や不要薬のリスクを減らすため、薬剤師の減薬提案がますます重要視されています。
本記事では、服用薬剤調整支援料1と2の違いから、算定の具体的な条件や記録方法、実際の運用例までを、図や表を交えながら徹底的に解説していきます。
算定ルールを誤ると返戻のリスクもあるため、しっかり確認して実務に活かしていきましょう!
- 服用薬剤調整支援とは?
- 服用薬剤調整支援料1とは?
- 服用薬剤調整支援料2とは?
- 服用薬剤調整支援料1と2の違いを比較
- 服用薬剤調整支援料2の報告書作成例と活用フロー
- 服用薬剤調整支援料2で荒稼ぎは可能?
- 服用薬剤調整支援料2の件数を簡単に増やすコツ
- 何を提案すればよい?やりやすい薬剤のポイント
- 残薬調整による減薬は支援料1を算定できる?
- 減薬してみたけど結局元に戻った…それでも支援料1は算定できる?
- 医科側でも算定できる点数があるの?
- 疑義照会で削薬してもらった場合、支援料1は算定できる?
- まとめ
- 服用薬剤調整支援に関するクイズ
- よくある質問(Q&A)
- 参考文献
- \忙しい薬剤師でもOK!最短で合格を目指すならココ/
- 悩んでいる時間がもったいない。今日から一歩踏み出そう!
服用薬剤調整支援とは?
服用薬剤調整支援とは、患者の薬物治療を安全かつ有効に継続するために、薬剤師が多剤併用や重複投薬、不要薬などを評価し、医師に対して減薬や変更の提案を行う業務です。
特に高齢者では、6剤以上の内服薬を服用しているケースが多く、副作用のリスクやアドヒアランス低下、相互作用などの問題が起こりやすくなります。
こうした背景から、薬剤師による処方提案や薬学的管理の重要性が高まり、調剤報酬の中で「服用薬剤調整支援料」として評価されるようになりました。
2020年度の調剤報酬改定では、この取り組みが「服用薬剤調整支援料1」および「服用薬剤調整支援料2」として制度化されました。
この制度の目的は以下の通りです:
- 不要な薬剤の整理(デパス®やメマリー®などの漫然投与)
- 多剤併用による副作用の予防(特に抗コリン作用やふらつき、低血糖)
- 重複投薬や相互作用の回避(複数病院受診者でのクラビット®重複など)
- 服薬遵守率の向上(分包数減や内服回数の簡略化)
- 薬剤費の削減と医療資源の効率化
薬剤師はこれらの目的を実現するために、処方内容の分析、患者ヒアリング、医師への提案、継続的なフォローといった専門的スキルを活かして取り組みます。

服用薬剤調整支援料1とは?
服用薬剤調整支援料1は、薬剤師の減薬提案により、患者の服用薬が2剤以上減り、その状態が4週間以上継続した場合に評価される調剤報酬です。
これは、薬剤師の提案が実際に処方に反映され、ポリファーマシーの是正という成果が認められた場合に限り、月1回・125点で算定できます。
算定の基本要件
- 対象患者:同一薬局で4週間以上継続して6種類以上の内服薬を処方されている患者
- 薬剤師の提案:処方医に対して文書で減薬提案を実施
- 減薬の結果:患者の内服薬が2剤以上減少(うち1剤は薬剤師の提案による)
- 経過観察:減薬後の状態が4週間以上継続している
レセプト記載事項
以下の情報をレセプト摘要欄に記載する必要があります:
- 調剤前後の内服薬剤数
- 医師への提案日・医療機関名
- 4週間後のフォロー実施日
カウント除外となる薬
- 服用期間が4週間未満の薬
- 屯用薬(必要時使用)
- 漢方薬(ただし主治医との合意があれば可)
- 同効配合剤への変更(例:ARB+Ca拮抗薬)
注意点
レセプト摘要や薬歴には「医師の同意を得た経緯」「患者との面談内容」などを詳細に記載することが、返戻防止につながります。
また、かかりつけ薬剤師指導料や重複投薬防止加算などとは併算定不可です。

服用薬剤調整支援料2とは?
服用薬剤調整支援料2は、薬剤師が他医療機関の処方を含めた薬剤全体を一元的に把握し、重複投薬や不適切な併用の可能性を検討・提案する取り組みを評価するものです。
支援料1とは異なり、実際の処方変更や減薬の結果ではなく、「提案そのもの」を評価する点が特徴です。
算定の基本要件
- 対象患者:複数医療機関から処方された内服薬が合計6剤以上の患者(うち1剤は自薬局で調剤)
- 薬剤一元管理:他院含めた全内服薬を把握(お薬手帳、本人ヒアリングなど)
- 提案・報告書:重複・相互作用等がある場合、医師に対して提案書または薬剤一覧報告書を作成・送付
- フォロー:次回来局時に処方内容が見直されているか確認
点数と算定回数
- 施設基準あり:100点/3ヶ月に1回
- 施設基準なし:90点/3ヶ月に1回
※施設基準ありとは、「過去1年以内に支援料1を1回以上算定している薬局」です。
レセプト記載事項
以下の内容をレセプト摘要欄に記載する必要があります:
- 提案書や報告書の送付日
- 対象となった薬剤の概要(例:重複薬名など)
- 患者の服薬状況と同意取得の有無
文書の扱いと様式
提案書や薬剤一覧の様式は指定されたフォーマットが推奨され、薬歴へ添付することが必要です。
また、同一内容での再提案は3ヶ月以内には算定できませんので注意が必要です。

服用薬剤調整支援料1と2の違いを比較
服用薬剤調整支援料1と支援料2は、目的は同じでも、評価のポイントが異なることが重要です。
以下に分かりやすく比較表をまとめました。
| 項目 | 服用薬剤調整支援料1 | 服用薬剤調整支援料2 |
|---|---|---|
| 評価対象 | 薬剤師提案による減薬の成果 | 薬剤師による重複投薬・不適切併用の提案 |
| 対象患者 | 同一薬局で4週間以上継続6剤以上 | 複数医療機関で6剤以上(うち1剤は自薬局) |
| 必要条件 | 2剤以上減薬、4週間継続 | 提案書または薬剤一覧を医師に報告 |
| 点数 | 125点/月1回 | 90点(施設基準なし) 100点(施設基準あり)/3ヶ月1回 |
| 評価のタイミング | 減薬の結果が出た後 | 提案や報告を行った時点 |
| 備考 | 併算定不可の加算に注意 | 様式指定の報告文書が必要 |
このように、支援料1は「結果型」、支援料2は「提案型」と覚えると、実務でも判断しやすくなります。

服用薬剤調整支援料2の報告書作成例と活用フロー
ここでは、支援料2を算定する際に必要な「報告書の書き方」と、「業務フロー」を具体的に解説します。
📄 報告書の作成例(テンプレート)
提出様式(例):「薬剤一元管理報告書」
| 患者氏名: | 〇〇 〇〇 |
| 作成日: | 2025年7月22日 |
| 提出先医療機関: | 〇〇クリニック |
| 薬局名: | 〇〇薬局 |
| 薬剤師氏名: | △△ △△ |
【薬剤一覧】
- 〇〇内科処方:リクシアナ15mg 1T 分1 朝
- ××整形処方:ロキソプロフェン60mg 1T 分3 毎食後
- △△皮膚科処方:フェキソフェナジン60mg 1T 分2 朝夕
【問題点の指摘】
- NSAIDsによる腎機能への影響が懸念される(高齢+抗凝固薬)
- 必要時使用への変更またはアセトアミノフェンへの切り替えを提案
【コメント欄】
服薬状況を患者本人に確認済み。服薬遵守状況は良好だが、2医療機関からの処方により薬剤重複の可能性あり。医師の判断で処方見直しをご検討いただければ幸いです。
📊 活用フロー図解(支援料2)
- 対象患者を抽出
複数医療機関から内服薬6剤以上の患者 - 一元的な薬剤管理
お薬手帳や本人ヒアリングで処方全体を把握 - 重複・相互作用等を評価
薬学的視点で問題を抽出 - 医師へ報告書提出
報告書または提案書を文書で送付 - 次回来局時に処方確認
見直しの有無に関わらず、取り組みは評価対象

服用薬剤調整支援料2で荒稼ぎは可能?
結論:荒稼ぎは難しいです。以下にその理由を詳しく解説します。
❌ 荒稼ぎが難しい理由
- 算定頻度が3ヶ月に1回のため、1人の患者から継続的に収益を得ることは難しい
- 報告書や記録が必須で、事務作業や薬歴の負担がかかる
- 施設基準がないと90点にとどまり、コストパフォーマンスは中程度
- 同一内容での繰り返し提案はNGなので、ネタ切れを起こしやすい
- 査定・返戻リスクもあり、形だけの提出は指導対象になる可能性がある
✅ 現実的な使い方とは?
地域支援体制加算の取得や、対人業務の積極的な取り組みの証明として活用するのが効果的です。
おすすめの活用例:
- 在宅訪問時に服薬全体を確認し、薬剤一覧を主治医に送付
- お薬手帳をもとに患者の薬歴を一元管理し、提案書として提出
- 複数の患者に3ヶ月サイクルで交互に提案し、支援料2の回転率を高める

- ✔ 支援料2は提案だけで算定可能で取り組みやすい
- ✔ しかし高頻度での算定が制限されており、収益源としては限界がある
- ✔ 地域支援体制加算の実績づくりや、対人業務の質向上には非常に有効
服用薬剤調整支援料2の件数を簡単に増やすコツ
支援料2の件数を効率的に伸ばすには、「対象者の選定力」と「テンプレート活用」がカギになります。
🎯 コツ①:在宅・複数診療科の患者を狙う
- 在宅訪問患者は複数科から薬が出ていることが多く、対象になりやすい
- 整形+内科+皮膚科など、受診科が3つ以上の患者はねらい目
📒 コツ②:お薬手帳を徹底チェック
- 手帳記載の他院処方を確認し、薬局で調剤していない薬も含めて管理
- 「いつもはこっちの病院でも薬出てるんだけど…」という情報が重要!
📝 コツ③:フォーマット化された報告書で時間短縮
- 薬剤一覧+問題点+コメントのテンプレートを準備しておく
- 重複や併用禁忌の指摘例をストックしておくと汎用性UP
📅 コツ④:月1〜2人ペースで“ずらして”提案
- 3ヶ月間隔なので、毎月2人ずつ交互に算定すれば月平均も安定
- 全体で年間8人いれば、実績としては十分
💬 コツ⑤:患者から情報を引き出すトーク力
- 「この前の病院では何か薬もらってますか?」の一言で対象が見つかることも
- ヒアリング力が算定件数を左右します!

何を提案すればよい?やりやすい薬剤のポイント
支援料2では「医師への提案」そのものが評価されるため、提案の根拠が明確で、妥当性があることが重要です。
📌 提案の根拠として使いやすい視点
- 漫然投与:明確な適応がなく、長期間継続されている薬剤(例:PPI、睡眠薬)
- 重複投与:複数科から同効薬・同系統薬が処方されている(例:NSAIDs、H2ブロッカー)
- 相互作用:薬物動態・薬力学上のリスクがある(例:抗凝固薬+NSAIDs)
- 高齢者の有害事象リスク:ベンゾジアゼピン、抗コリン薬など
- 腎機能・肝機能低下時の過量投与:腎排泄性薬剤(例:ガバペン®、メトトレキサートなど)
✅ 提案しやすい薬剤の特徴
以下のような薬剤は、文献やガイドライン上でも中止・減量・適正化が推奨されており、提案しやすいです。
- ▼ ベンゾジアゼピン系:高齢者の転倒・認知機能障害リスク
- ▼ NSAIDs:腎機能・出血リスク(特に高齢+DOAC併用)
- ▼ 抗コリン薬:便秘・せん妄・排尿障害
- ▼ PPI:ピロリ除菌後の漫然継続・骨折リスク
- ▼ 認知症薬:効果不明・中止判断に迷うケースが多い
📎 例文での表現ポイント
- 「本剤は高齢者において有害事象リスクが高く、必要性を再検討いただくことをご提案いたします」
- 「腎機能低下が認められる患者にNSAIDsの継続投与があるため、処方内容の見直しをご検討願います」
- 「お薬手帳より、同一系統薬の重複処方が疑われます」

残薬調整による減薬は支援料1を算定できる?
服用薬剤調整支援料1は、薬剤師の提案によって実際に「医師が処方を減らし」、その減薬状態が4週間以上継続したことを評価する制度です。
📌 「残薬あり」理由の処方減少は対象外
- 一時的な処方薬数の減少(たとえば「今月は残薬あるので○剤処方中止」など)は医師の処方方針の変更とは見なされません
- 次回の処方で元の薬数に戻る可能性が高いため、「4週間以上継続した減薬」には該当しません
- 算定には、薬剤師の減薬提案が処方医に受け入れられた事実が必要です
📝 厚労省Q&Aや実務上の注意点
調剤報酬Q&A(厚労省)や実地指導では以下のように説明されています:
- 「薬剤師の提案に基づく処方変更がなければ支援料1は算定不可」
- 単なる服薬アドヒアランスの改善や残薬整理のみでの算定はできません
- 「残薬調整により処方薬数が減っただけ」は査定の対象になることがあります
✅ 正しい支援料1の算定例
- 例:薬剤師がベンゾジアゼピンの減量を提案 → 医師が1剤中止 → 処方上2剤減 → 4週間継続
- → このように、「医師の処方内容」が薬剤師の提案で変更されていることがポイントです

減薬してみたけど結局元に戻った…それでも支援料1は算定できる?
服用薬剤調整支援料1の算定には、減薬後の状態が4週間以上継続していることが必須条件です。
📌 一時的な減薬ではNG
- 減薬後、患者の病状悪化や効果不足などにより薬剤が復活した場合
- 医師が「一旦止めて様子見」と判断し、後日再開した場合
このようなケースでは、薬剤師の提案が最終的に「治療方針として採用された」とは言えないため、支援料1の算定要件に該当しません。
📌 指導や査定リスクも
- 「一時的な減薬でも算定した」とレセプトで見なされると返戻や個別指導の対象になりえます
- 薬歴・摘要欄に「〇日減薬→再開」などの記載があると根拠が崩れるため注意
✅ 逆に算定可能なパターン
- 薬剤師の提案により2剤以上の内服薬が処方から削除
- 4週間以上、その状態が維持された(=医師の治療方針として定着)
- 医師の同意と患者の了解が記録されている

医科側でも算定できる点数があるの?
薬局薬剤師が「服用薬剤調整支援料1・2」で介入した場合、医科側でも対応する加算が算定できる制度があります。
💡 薬剤総合評価調整管理料とは?
薬剤総合評価調整管理料は、医師が薬剤師からの報告(薬剤一覧・減薬提案など)をもとに処方を見直した場合に評価される点数です。
- 対象:複数の医療機関・薬局から処方されている患者
- 要件:薬剤師の情報提供(文書)があること
- 目的:薬物治療の適正化、医薬連携の強化
📌 連携の流れ(例)
- 薬局で「支援料1または2」を目的に減薬・重複提案
- 薬剤一覧・報告書を医師へ提出
- 医師が内容を踏まえ、処方を見直す
- 医科側で「薬剤総合評価調整管理料」を算定
このように、薬局と医療機関の連携は、双方の加算を成立させる形となり、「連携実績」や「地域支援体制加算の根拠」としても有用です。
📎 注意点
- 医師は報告書を「参考にして処方を調整」したという記録が必要
- 薬剤師の提案が文書であることが条件(口頭のみは不可)
- 報告がなければ医科での加算は算定不可

疑義照会で削薬してもらった場合、支援料1は算定できる?
服用薬剤調整支援料1は、薬剤師の提案で2剤以上減薬され、その状態が4週間以上継続していることが要件です。
📌 疑義照会による減薬も「提案」として認められる
- 薬剤師が処方意図を確認し、不要と思われる薬剤を提案して中止された場合
- その変更が「患者の薬物治療に関して専門的な意見」であり、医師が了承した場合
これらは、文書でなく口頭の疑義照会でも構いませんが、薬歴やレセプト摘要欄に「薬剤師提案により中止」と明確に記載する必要があります。
✅ 疑義照会による算定の具体例
- 例:抗コリン薬の便秘副作用に気づいた薬剤師が医師に中止を提案 → 同意 → 処方変更
- 例:同効薬の重複を発見し、疑義照会で1剤削除 → 減薬成立
⚠ 注意点
- 医師の処方ミス修正(例えば誤記)や単なる確認対応は「提案」扱いにならず、算定不可
- 減薬が1剤のみ、または4週間以内に元に戻った場合も不可

まとめ
服用薬剤調整支援料は、薬剤師が患者の薬物治療を最適化する取り組みを評価する重要な点数です。
📌 支援料1(成果型)
- 薬剤師の提案で処方薬が2剤以上減り、4週間以上継続していることが条件
- 実際に処方変更されたという「成果」が必要
- 疑義照会による減薬もOK(記録必須)
📌 支援料2(提案型)
- 提案・報告書の提出があれば、処方変更の有無は問われない
- 複数医療機関から薬が出ている患者が対象
- 報告様式や薬歴記載の整備がポイント
✅ 実務での活用ポイント
- 支援料2は導入しやすく、地域支援体制加算の実績づくりに最適
- 在宅・複数科受診患者を中心に取り組むと件数が伸びやすい
- 減薬候補薬は、ベンゾ系、NSAIDs、PPI、抗コリン薬などが狙い目
⚠ 注意点
- 残薬調整や一時的な中止は支援料1には算定できない
- 4週間継続が必須/再開されてしまうと不可
- 不適切な繰り返し算定や書類不備は査定リスク

服用薬剤調整支援に関するクイズ
第1問:支援料1を算定できるのは、次のうちどのケース?
- A. 残薬があるため医師が一時的に2剤を処方中止した
- B. 薬剤師の提案で2剤減薬され、4週間継続している
- C. 自主的に患者が服薬をやめた
正解:B
支援料1では、「薬剤師の提案により2剤以上が中止され、4週間以上その状態が継続している」ことが条件です。一時中止や自己判断は算定できません。
第2問:支援料2で実際に処方変更がなかった場合、算定できる?
- A. はい、提案と報告書があればOK
- B. いいえ、処方変更が必要
- C. 医師の了承が口頭でもあればOK
正解:A
支援料2は「提案型」の評価です。実際の処方変更や採用の有無は問われず、薬剤師からの情報提供・報告書作成が評価されます。
第3問:支援料2の算定上限頻度は?
- A. 月1回
- B. 3ヶ月に1回
- C. 年1回
正解:B
支援料2は3ヶ月に1回まで算定可能です。3ヶ月未満での同様の内容による再提案は算定不可とされています。
よくある質問(Q&A)
服用薬剤調整支援料1と2は同時に算定できますか?
いいえ、支援料1と2は同月に重複算定はできません。いずれか一方のみ算定可能です。優先すべきは「成果型」の支援料1ですが、提案だけで評価される支援料2も有効に使い分けましょう。
支援料1の「2剤以上減薬」には、配合剤への変更も含まれますか?
いいえ、同効配合剤への切り替えによる剤数減はカウントされません。実際に薬理作用を持つ薬剤の種類数が減ったことが条件です。
支援料2の報告書は手書きでも良いですか?
はい、形式は自由ですが、「誰が・いつ・何を」報告したかが明確であれば手書きでも構いません。PDFや様式テンプレートも活用されることが多いです。
一度支援料1を算定した患者に、再度支援料1を算定できますか?
はい、再算定は可能です。条件は、「さらに2剤以上の減薬が新たに発生し、その状態が再度4週間継続した場合」です。前回の減薬内容とは別の新たな提案であることが必要です。
残薬があるために処方されなかった薬は、減薬としてカウントされますか?
いいえ、残薬整理のための処方中止は医師の処方方針変更とはみなされません。支援料1の算定条件は「薬剤師の提案による処方変更と4週間以上の継続」です。
支援料2の対象患者はどうやって見つけるのが良いですか?
複数の病院を受診している高齢者、在宅患者、薬剤数が多い患者が該当しやすいです。お薬手帳のチェックや患者ヒアリングが有効です。
医師に処方を戻されてしまったら支援料1は無効ですか?
はい、4週間継続しないまま元に戻った場合は算定できません。提案した事実のみ評価される支援料2に切り替えて対応するのが安全です。
参考文献
- 【Pharmacist.M3】服用薬剤調整支援料1・2の算定要件や違い
- 【ナナファーマシスト】服用薬剤調整支援料1・2の算定要件(2024年改定)
- 【MedPeer】服用薬剤調整支援料2の原文要件
- 【薬読】服用薬剤調整支援料1の詳細と支援料2との違い
- 【薬読】薬剤総合評価調整管理料(医科側の加算)








\忙しい薬剤師でもOK!最短で合格を目指すならココ/
【呼吸療養認定士】吸入指導のエキスパートへ!
「吸入薬、うまく使えてないな…」という患者さん、多くないですか?
この資格があれば、吸入デバイス指導から生活指導まで、医師に一目置かれる存在に。
✅ 呼吸器疾患への薬物療法が体系的に理解できる
✅ COPDや喘息の服薬アドヒアランスに貢献
✅ 地域包括ケアでの活躍チャンス拡大!
【透析技術認定士】電解質・水分管理の知識が武器になる!
透析患者の処方、なんとなくで扱っていませんか?
この資格で「透析処方が読める薬剤師」になれます。
✅ 血液・腹膜透析の薬学的視点がしっかり学べる
✅ 高カリウム血症やP管理などのアセスメント力がアップ
✅ チーム医療の中で活躍の場が広がる!
【認知症ケア認定士】「ただの服薬指導」からの脱却!
認知症の方との会話に困ること、ありませんか?
この資格で「認知症に寄り添える薬剤師」になれます。
✅ BPSD(行動心理症状)への対応知識も学べる
✅ 在宅・施設での多職種連携がスムーズに
✅ ケアマネや家族からの信頼も高まる!
【糖尿病療養認定士】薬だけじゃない、生活まで支える力!
HbA1cばかり見ていませんか?
この資格があれば、「生活までアドバイスできる薬剤師」に。
✅ 食事・運動・インスリンまで包括的に学べる
✅ SMBG・インスリン注射の技術支援にも対応
✅ 外来・薬局・在宅、どの現場でも活躍できる!
悩んでいる時間がもったいない。今日から一歩踏み出そう!









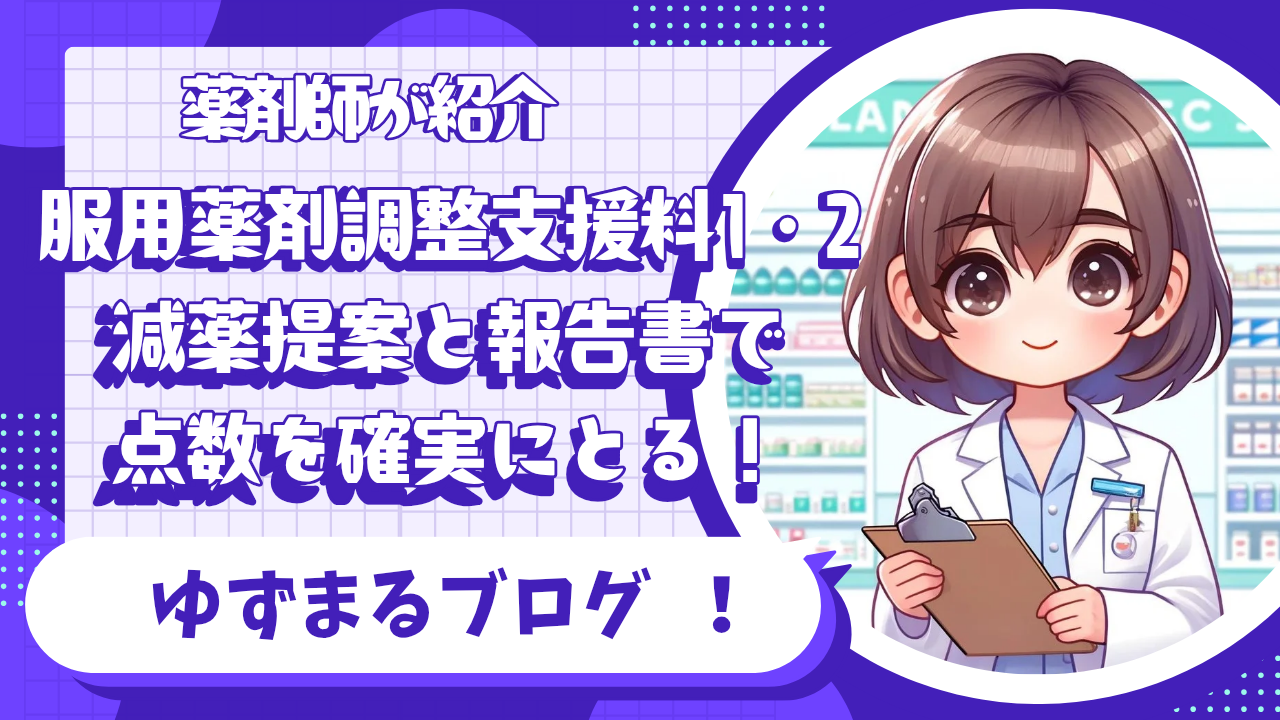

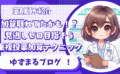
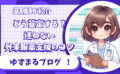
コメント