

前書き:第三者行為=「健康保険が一時立替 → あとで加害者へ求償」
交通事故・傷害など第三者の行為が原因の負傷でも、原則として健康保険は使えます。ただし被保険者(患者)側に「第三者行為による傷病届」の提出義務が生じ、保険者は後日、加害者等へ立替分を請求(代位取得・求償)します。制度の根拠は健康保険法第57条で、保険者が立替分の範囲で損害賠償請求権を取得します。
つまり薬局の役割は、
- (1)窓口トリアージ(事故かどうかの確認)
- (2)患者さんへ届出と示談の注意喚起
- (3)レセプトの正しい記載(「10・第三」等)
- (4)事故外点数の整理です。
これらを順番に、現場で迷わないレベルまで噛み砕いて解説します。
第三者行為の基礎知識(超要点)
- なぜ届出が必要?:健康保険が本来加害者負担の医療費を一時立替するため。保険者があとで加害者へ請求するうえで、事故状況の届出が不可欠。
- 法的根拠:健康保険法第57条(代位取得・求償/重複補填の調整)。
- 提出期限の目安:国保では「利用開始からおおむね1か月以内に届出」をルール化(損保団体との取決め)。実務でも早めの案内が安全。
- 示談の落とし穴:医療費を含む示談や「医療費請求を放棄」する示談は、以後の健保利用に支障・自己負担化リスク。患者に示談前連絡を必ず促す。
薬局の実務フロー:受付〜算定〜請求まで
1)受付・問診で「事故かどうか」を最初に確認
受付時に受傷原因・受傷日・事故種別(交通事故・喧嘩・スポーツ等)を確認。
交通事故であれば自損・同乗・対物のみか/人身切替予定かも聞き取り、薬歴に記録します。
同乗者でも運転者が加害者となりうるため、同乗者のレセプトには「10・第三」が必要になる点は実務での見落としポイント。
2)患者への案内:必ず届出、そして示談は保険者へ先に相談
- 届出書類:第三者行為による傷病届および添付(交通事故証明書、人身事故証明書入手不能理由書など)。協会けんぽの様式・添付要件が分かりやすいのでリンクを案内。
- 提出先:患者の加入保険者(協会けんぽ/健保組合/市町村国保 等)。
- 注意喚起:勝手に示談しない(医療費を含む示談や放棄条項で健保不使用・自己負担化の可能性)。
3)レセプト記載:特記事項欄に「10・第三」を必ず入れる
厚労省の「明細書記載要領」に基づき、第三者行為該当レセプトの特記事項欄へ「10・第三」を記載するのが義務付け。月跨ぎでも継続して毎月記載します(事故点数の記載だけでは不十分)。
明細書記載要領(様式・摘要欄等の一般取扱い)は最新通知を常に参照しましょう。
4)事故外点数の扱い(混在時)
事故(第三者行為)由来の投薬と、関係のない慢性疾患等が同月に混在する場合、事故該当分に「10・第三」、事故外分は「事故外点数」を摘要等で区別して明記。査定・返戻防止の基本です。
5)窓口負担の取り扱い
患者一部負担金の扱いは、保険者・事故相手の損保・本人の希望等で運用差があります。
基本は通常どおりの一部負担金を受領し、後日、損保・加害者から患者へ精算される運用が多いですが、ケースにより異なるため事前に患者・保険者・損保と整合を取ると安全です(制度上の代位取得の考え方は各健保の案内が分かりやすい)。
よくあるハマりどころと回避術
示談を先にしてしまった
医療費を含む示談成立後は、以降の健保適用ができない/自己負担化することがあります。
示談前に必ず保険者へ連絡するよう患者に案内し、薬局でもポップ等で周知しましょう。
自損事故・同乗者の扱い
「同乗者=被害者」のケースでも、運転者が加害者となりうるため、同乗者のレセプトにも「10・第三」を忘れずに。
国保の届出タイミング
国保では利用開始からおおむね1か月以内に届出を求める取決めが示されています。社保・組合健保でも「早めの届出」を強く推奨。
労災との関係
業務上・通勤災害は原則、労災保険が優先(健康保険の対象外)。
一方、「第三者行為」は民間人同士の事故等で健保が一時立替 → 加害者へ求償する仕組み。重複補填の排除(支給調整)の考え方は労災でも同様で、政府が給付した場合は第三者に求償するルールが明確です。
書き方テンプレ(薬局用メモ)
- 特記事項欄:
10・第三(毎月)+「事故日:YYYY/MM/DD」「加害者種別(自動車・自転車等)」を摘要で補足すると親切。 - 混在時:事故由来と事故外を明確化(事故外点数の明記)。
- 書類案内:第三者行為による傷病届/交通事故証明書/人身事故証明書入手不能理由書(必要時)。
- 薬歴記録:受傷原因・日時・部位・示談有無の説明・届出案内を記録。
症例で学ぶ:レセプトと窓口対応の実践
症例1:自転車同士の接触で転倒、鎮痛薬と湿布を院外処方
確認事項:第三者(相手自転車)関与/受傷日/警察届出の有無。
窓口案内:協会けんぽ加入→「第三者行為による傷病届」提出を案内。交通事故証明書が出ない場合は警察事故受理番号や人身切替の予定等を確認。
レセプト:「10・第三」を記載。慢性片頭痛の定期処方と同月なら、事故外点数で区別。
症例2:車同乗者としてムチウチ、湿布とPPIが同時処方
確認事項:同乗者であっても第三者行為該当(運転者が加害者となりうるため)。
レセプト:ムチウチ関連は「10・第三」。既往の逆流性食道炎で増量になったPPIは事故誘発性が不明なら「事故外点数」に分ける。
症例3:国保加入者の軽微な接触事故、患者が「そのうち示談」と発言
注意喚起:「医療費を含む示談」や「医療費請求放棄」を含む合意は、以後の健保利用を妨げる可能性がある。示談前に必ず保険者へ相談。国保は1か月以内届出の運用があり、早めの届出が無難。
PR(第三者行為の現場で役立つ“事務スキル強化”)
【PR】調剤事務の知識を体系的に身につけたい方へ
まとめ:第三者行為は「早めの届出」×「10・第三」×「事故外区分」
- 患者には届出と示談注意を明確に案内(様式・添付も)。
- レセプトは毎月「10・第三」、混在時は事故外点数も。
- 国保は1か月以内届出の運用があり、迅速対応が吉。
- 根拠は健康保険法第57条(代位取得・求償)で、重複補填は不可。
よくある質問(FAQ)
Q. 交通事故でも健康保険は使えますか?
A. はい、使えます。ただし「第三者行為による傷病届」の提出が前提で、保険者が後日加害者に求償します。示談前には必ず保険者へ相談を。
Q. レセプトでは何を必ず書きますか?
A. 特記事項欄に「10・第三」を必ず記載。治療が複数月続く場合も毎月記載。
Q. 事故に無関係の慢性薬が同月にあります。どう区別?
A. 事故分は「10・第三」、事故外は「事故外点数」等で明確に区別して記載します。
Q. 同乗者でも第三者行為ですか?
A. 多くのケースで該当します(運転者が加害者側になるため)。同乗者レセプトにも「10・第三」を。
Q. 国保ですが、届出はいつまで?
A. 目安として利用開始から1か月以内に届出する運用が示されています(損保団体との取決め)。
併せて読みたい関連記事
参考文献(WEB一次情報中心)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「事故にあったとき(第三者行為による傷病届等について)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3260/r143/(最終確認:2025-09-26) - 全国健康保険協会「第三者行為による傷病届(様式・添付書類)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat295/r454/(最終確認:2025-09-26) - 協会けんぽ 愛媛支部「医療機関の皆様へ:第三者行為該当レセプトの特記事項記入について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/ehime/cat080/medical/2394-16171/(最終確認:2025-09-26) - e-Gov法令検索「健康保険法 第57条(代位取得・求償)」
https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070(最終確認:2025-09-26) - 法令リファレンス「健康保険法 第57条(条文抜粋)」
https://hourei.net/law/211AC0000000070(最終確認:2025-09-26) - 厚生労働省「第三者行為による被害に係る求償事務の取組強化について」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1884&dataType=1(最終確認:2025-09-26) - 健康保険組合連合会「交通事故(第三者行為)に関する傷病届の作成支援」
https://www.kenporen.com/health-insurance/traffic-accident/traffic-accident.pdf(最終確認:2025-09-26) - JR健康保険組合「交通事故など第三者の行為により病気やけがをしたとき」
https://www.jrkenpo.or.jp/procedure/accident/(最終確認:2025-09-26) - 厚生労働省 東京労働局「第三者行為災害について(労災の支給調整と求償)」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/ro-3.html(最終確認:2025-09-26) - 厚生労働省 通知「診療報酬明細書の記載要領(様式関連)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001275316.pdf(最終確認:2025-09-26)
薬局で働いていると、どうしても避けられないのが「人間関係のストレス」。 そんな現場のリアルな悩みに向き合うために、管理薬剤師としての経験をもとにまとめたのが、この一冊です。 『薬局長のためのモンスター社員対応マニュアル』 薬局で起こりやすい“モンスター社員”を15タイプに分類し、 薬局で人に悩まないための「実践マニュアル」として、 「薬局長が守られれば、薬局全体が守られる」 📕 シリーズ第1弾はこちら 📘『薬局長のためのモンスター社員対応マニュアル』発売のお知らせ
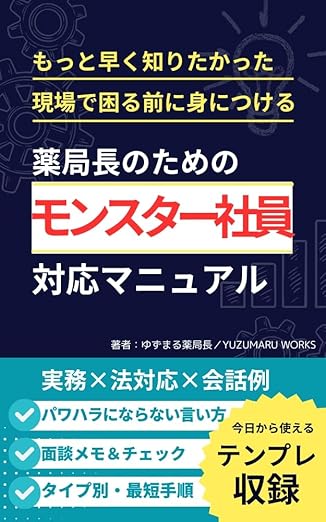
患者対応、スタッフ教育、シフト調整……。
気がつけば、薬局長がいちばん疲れてしまっている。





― 現場で困る前に身につける 実務 × 法対応 × 会話例 ―
それぞれの特徴・対応法・指導会話例を紹介。
パワハラにならない注意方法や、円満退職・法的リスク回避の実務ステップも具体的に解説しています。
日々の業務の支えになれば幸いです。
現場の“声にならない悩み”を形にしました。
📘 書籍情報
👉 『薬局長になったら最初に読む本』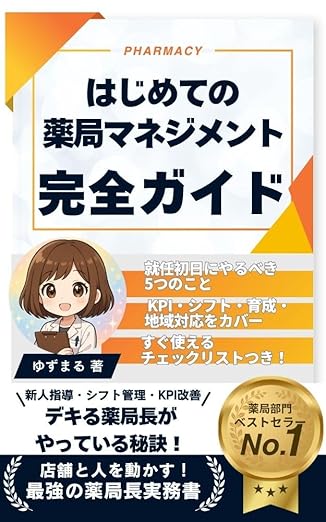







カウンターでそう言われるたび、私の言葉が届いているのかなって不安になります。

だからこそ糖尿病療養指導士。
薬を渡すだけじゃなく、行動が変わる言葉まで一緒に学べる。
あの人の「できた!」を増やせる資格だよ。
患者さんの“続けられる”を作る専門家。
GLP-1/GIPなど新薬の説明も、生活に落とし込める言葉へ。
- 血糖パターン(食後高血糖/早朝高血糖)を“見える化”して説明
- 低血糖予防とリカバリの即実践テンプレ
- 食事・運動・睡眠を“続けられる小さな約束”に翻訳
カウンターで詰まらないための、使える順の学び。
明日の声かけが、患者さんの1週間を変える。
- 薬理×生活:GLP-1/GIP・SGLT2・DPP-4・インスリンの“患者目線”説明
- 血糖自己測定/フラッシュCGMの活用とフィードバックの型
- 合併症予防のミニ目標(歩数・食事・睡眠)を一緒に設計

申し込み、今します。

さあ、いっしょに行こう🍀

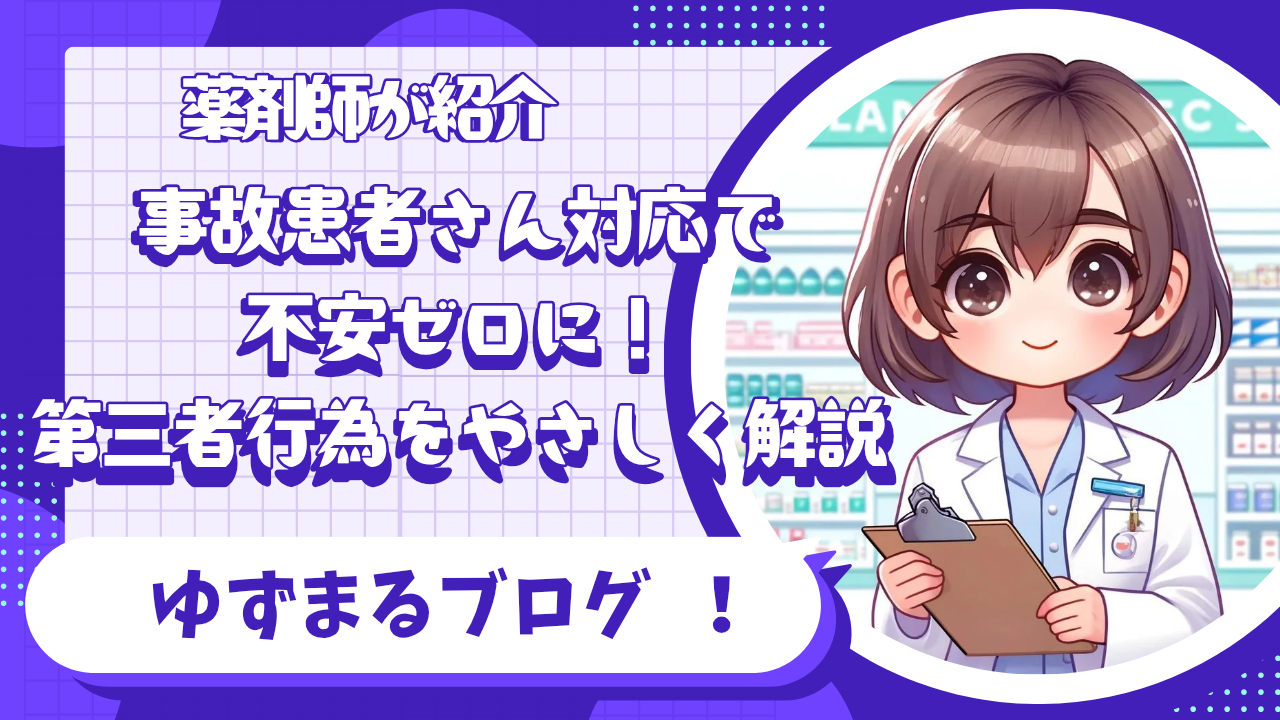

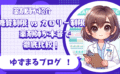
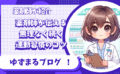
コメント