speech-person”>



薬局薬剤師として働く中で、患者さんの服薬支援は日常業務の大切な一部です。中でも、外来服薬支援料1は、服薬管理に課題を抱える患者さんへの支援を評価する加算であり、2024年度の診療報酬改定以降、地域支援体制加算の要件のひとつにも位置づけられるようになりました。
しかし現場では「どうやって対象患者を見つけるの?」「何を記録すればいいの?」「医師への報告はどうするの?」といった悩みが多く、なかなかうまく活用されていないのが実情です。
この記事では、実務に即した支援料1の効率的な算定方法を、薬局で明日からすぐに使える形で紹介していきます。
服薬支援の質を高めながら、業務の効率化と収益の向上につなげたい方は、ぜひ参考にしてください。
外来服薬支援料1の算定条件は?
まずは算定の基本条件を正確に把握しておきましょう。
条件を理解していなければ、どれだけ努力しても加算は取れません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 点数 | 185点(1回/月) |
| 対象 | 服薬支援を必要とする外来患者(処方箋有無問わず) |
| 支援内容 | 一包化、服薬カレンダー使用、飲み忘れ防止策など |
| 医師との連携 | 事前の了解 または 事後の報告が必須 |
| 記録要件 | 薬歴への詳細な記録(支援理由・内容・結果) |
| 併算定不可 | 外来服薬支援料2や在宅訪問との同月算定は不可 |

効率よく算定するための3つの戦略
① 対象患者を見逃さないチェック体制を作る
服薬支援が必要な患者は、見た目では分かりません。事前にチェックリストや対象基準を明確にしておくことが算定数UPの鍵です。
- 65歳以上かつ多剤(6剤以上)服用
- 飲み忘れ・残薬が頻繁にある
- 認知機能の低下が見られる(会話や受け答えで判断)
- 服薬タイミングが複雑(1日3回以上や間隔制限など)

② 医師とのスムーズな連携ルートを確保
医師の了解または報告がなければ絶対に算定できないため、連携体制の整備が重要です。
Faxテンプレートや電子共有ツール(地域連携システム、クラウド)を活用し、支援内容を明確に伝えましょう。内容は以下を含めると丁寧です。
- 患者の課題(服薬アドヒアランス、残薬など)
- 支援方法(整理方法、一包化、服薬タイミング)
- 支援の結果と今後の対応
③ 支援内容のテンプレート化と薬歴記録の強化
薬歴記録が不十分だと、算定が否認される可能性もあります。以下のような構成で記録しましょう。
【支援理由】多剤併用による飲み忘れ頻発 【支援内容】服薬カレンダーを使用し、朝・昼・夜で分包し整理 【結果】残薬確認しながら使用中、次回来局時に残薬量を確認予定 【報告】医師にFaxで事後報告済(2025年7月)
このように、患者支援の全体像を把握→支援→記録→報告という流れを標準化することで、効率よく件数を積み上げることができます。
外来服薬支援料1を狙いやすい患者とは?
支援料1は「服薬が自己管理できない or 管理が困難な患者」が対象です。
以下に、現場で見逃しがちな狙いやすい患者像を紹介します。
① 多剤併用かつ高齢の患者
65歳以上で6剤以上を常用している患者は、認知機能や操作能力の低下により服薬ミスが起こりやすい傾向があります。
特に以下のような状況は要注意です。
- 「朝・昼・夕・就寝前」の4回以上の服用タイミング
- 1包に入る錠数が多く、飲み間違いが起きやすい
- 残薬確認時に「前の分がまだある」と言われる
② 認知症や軽度認知障害(MCI)の患者
処方歴が一定で残薬が毎回出る患者は、MCIの可能性があります。
以下のような兆候が見られたら支援対象にできます。
- 同じ質問を何度も繰り返す
- 「薬は飲んでるよ」と言うが残薬は減っていない
- ご家族から「最近忘れっぽくなった」との申し出がある

③ 1人暮らしの高齢者+通院困難者
服薬管理だけでなく、生活全般に課題を抱えるケースが多いため、カレンダー投薬や支援用チェックリストなど、整理整頓型の支援が有効です。
④ 飲み忘れや自己中断が頻繁な患者
服薬アドヒアランス不良の患者(抗うつ薬、糖尿病薬、抗精神病薬など)は、支援介入によって行動変容が見込まれます。
中断理由を確認し、支援提案→報告することで算定対象にできます。
⑤ 複数医療機関から処方がある患者
重複投薬や服用タイミングのズレがある場合、服薬支援によって調整・提案・整理を行うことで、支援料1のエビデンスが成立します。
- 循環器内科+整形外科+精神科など、異なる診療科で薬が重なる
- 薬局ごとに包装形態や服用指示がバラバラ
- 調剤併用歴が確認できる場合、特に推奨
支援料1の「狙い目5タイプ」
- 高齢×多剤+複雑な服薬タイミング
- 認知機能に不安のある患者
- 独居や通院困難の高齢者
- 服薬中断や自己判断の多い患者
- 多施設・多診療科処方を受けている患者
これらの患者を「薬局全体で毎月ピックアップ」する運用体制をつくれば、年間で12〜20件以上の算定も十分に可能です。
2科受診(整形外科と内科)、どちらに報告すべき?
外来服薬支援料1を算定する際、複数の医療機関から処方がある患者の場合、どの医師に支援結果を報告すべきか悩むことがあります。
基本方針:主たる管理を行う医師に報告
報告先は「患者の全身状態や薬物治療を総合的に管理している医師」を選ぶのが原則です。
| 判断基準 | 報告先 |
|---|---|
| 処方薬の大半が内科医から | B病院 内科医に報告 |
| 飲み間違いの原因が整形薬にある | A病院 整形外科医に報告 |
| 一包化や服薬整理が複数の薬にまたがる | 主治医(内科)に報告が無難 |
報告は1医師でOK、必要に応じてダブル報告も可
基本的には1人の医師への報告で十分です。ただし、2医療機関の連携が重要なケースでは両方に同じ報告を送るとより丁寧です。
実際の報告文サンプル(Fax送付用)
○○薬局 ●年●月●日 患者:田中花子(78歳) 処方元:A病院 整形外科、B病院 内科 【支援内容】 ・両医療機関の処方薬を服薬カレンダーで時系列整理 ・朝:骨粗鬆症薬+降圧薬、昼:NSAIDs、夜:糖尿病薬+鎮痛剤 ・視覚的に整理することで誤飲リスクを軽減 【支援理由】 ・前回の来局時に残薬多数、服薬タイミングの混乱を確認 ・一包化は患者希望により実施せず ・今後も月1回、服薬状況確認予定 ※事後報告として送付いたします。

【重要】再分包したケースで外来服薬支援料1は取れない?
❌ 疑義解釈で「再分包では不可」と明言
厚生労働省の保険調剤Q&A(令和6年度版Q143)では、服薬途中で医師から中止指示があり、すでに分包された薬剤から当該薬を除去し再分包した場合は、外来服薬支援料1は算定できないと明記されています。
📌 なぜ算定不可なのか?
- 本来の支援目的(一包化やカレンダーによる服薬フォロー)が成り立たないため
- 再分包は調剤行為に該当し、「再調剤+再分包」であるため別評価の対応が妥当
再分包後に取れる可能性のある算定:再調剤料や一包化加算
再分包は調剤のやり直しと考えられるため、再調剤料や一包化加算(外来服薬支援料2)として評価される可能性があります。
ただし、現時点では調剤報酬として請求できるものはありません。

✅ 実務的対応のポイント
- 再分包ではなく、服薬カレンダーの整理のみ行い、A薬は残薬として扱うなど支援の枠組みで対応
- それが難しい場合は、在宅訪問薬剤管理指導料(居宅対応)に切り替えることで再評価対応が可能
すでに分包済の薬からA薬だけを抜いて再分包する行為は、外来服薬支援料1としては算定不可です。
✅ 一包化後に薬を抜いて新薬を入れる場合の算定
ケース整理
- 一包化後にA薬が変更・中止
- 医師指示を受け、A薬を除去して新たに処方された薬を追加し再分包
結論:算定できる可能性あり
厚労省のQ&Aや実務運用では、「持参薬等を回収し、医師の了承のもと再分包」する行為、外来服薬支援料1の算定対象となるとされています。
群馬県社保委員会のQ&Aでも同様の判断が示されており、一包化済薬からの抜き換えを含む再分包が支援料1として算定可能とされています。
重要なポイント
- 医師の一包化・再分包の指示を必ず取得
- 持参薬含め「整理・再パック」を明確に支援として実施
- 薬歴に指示内容、整理方法、結果を詳細に記載
- 処方元医師へ事後報告(または事前了解)
薬歴記載例
【支援理由】A薬中止のため再整理・新薬追加の必要性あり 【支援内容】持参薬+新処方薬を回収→A薬を除去し再分包実施 【結果】誤服リスク軽減。本人理解あり。 【連携】A病院医師にFaxで事後報告済
一度分包された薬から薬剤を抜いて、新薬を追加して再分包する行為は、医師了承・整理目的・支援行為として実施されるならば、外来服薬支援料1の算定対象となります。
ただし、必ず医師指示・薬歴記録・整理実施がセットであることが前提です。
患者から他院の薬を預かるのはOK?
原則:預かりは不可
薬局で患者からA病院の薬を預かる行為は、薬局の許可業務の範囲外とされており、原則として認められていません。
薬局には「自ら調剤した薬を交付・管理する責任」があるため、他医療機関の薬を預かることは薬剤師法・薬機法の観点から不適切とされます。
例外的に認められるケース
ただし、以下のような状況で一時的かつ目的限定で薬を預かる場合は、現場裁量として許容される可能性があります。
- 疑義照会中:処方内容に疑問があり、医師の確認を待っている
- 災害時・体調不良等:すぐに服薬指導が困難な緊急事態
- 訪問前の持参薬確認:在宅対応などで患者の薬剤状況を一時確認したい
実務上の対応ポイント
- 患者または家族の口頭または書面同意を得る
- 預かり目的を明確に記録(薬歴または別紙)
- 薬は個別に仕分け・混在させず、保管期限を設定
- 原則としてその日中に返却または処理完了とする
注意点とリスク
預かり行為は、薬剤の紛失・誤交付・温度管理など多くのリスクを伴います。記録の不備や本人確認のミスが重大事故につながる可能性があるため、極力避けるべき行為です。

一包化加算と外来服薬支援料1、薬局にとって得なのはどっち?
それぞれの基本点数
| 項目 | 点数 | 概要 |
|---|---|---|
| 一包化加算(2剤以上) | 日数に応じて最大240点 | 服用時点ごとの一包化 |
| 外来服薬支援料1 | 185点(月1回定額) | 服薬支援+医師連携+薬歴記録 |
一包化加算の点数表
| 投与日数 | 加算点数 |
|---|---|
| ~7日 | 34点 |
| 8~14日 | 68点 |
| 15~21日 | 102点 |
| 22~28日 | 136点 |
| 29~35日 | 170点 |
| 36~42日 | 204点 |
| 43日以上 | 240点 |
どちらが得?ケース別比較
- 30日処方: 一包化加算 170点 < 支援料1 185点 → 支援料1が得!
- 43日処方: 一包化加算 240点 > 185点 → 一包化加算が得!
業務負荷と地域加算の関係
- 一包化加算: 調剤内完結・記録簡単・地域支援体制加算にはカウントされない
- 支援料1: 記録・報告・医師連携が必要・地域支援体制加算の算定実績になる
結論
- 📅 短期処方: 外来服薬支援料1の方が収益性良好
- 📆 長期処方(36日以上): 一包化加算が高得点で有利
- 🧩 戦略: 両者をうまく使い分けて、件数・収益・体制加算のバランスをとる

【具体症例】多剤・MCI疑い患者への服薬支援
患者情報
- 患者:78歳 女性(独居・要介護1)
- 主病:糖尿病・高血圧・変形性膝関節症
- 処方:内科(B医院)から5剤/整形外科(A病院)から3剤
- 服薬状況:1日4回の服用時点・残薬多数あり・自己判断で服薬中止歴あり
問題点
- 飲み忘れ多数(特に昼食後の薬)
- 朝と夕の薬が混在し、誤服歴あり
- 「この薬何のためか分からない」との発言あり
- MMSE簡易チェックで記銘力に軽度の低下
支援内容
- 1週間分を服薬カレンダーに色分け整理
- カレンダーは「朝・昼・夕・寝前」の4区分
- 整形と内科の薬をまとめてタイミング調整
- A病院・B医院それぞれに内容を報告
- 服薬チェックシートも一緒に提供
薬歴記録(抜粋)
【対象理由】1日4回の複雑な服薬+MCI傾向+残薬多数+誤服歴あり 【支援内容】服薬カレンダーを用い、朝昼夕寝前で視覚的整理。自己判断での中止薬あり。整形・内科処方を統合して整理。 【結果】本人「わかりやすくなった」「全部出してくれると助かる」と好反応。家族に使用方法説明済。 【報告】B医院(内科)へFaxで事後報告済。整形は患者同意により省略。
算定・実績
- 外来服薬支援料1:185点を算定(査定なし)
- 服薬支援として地域支援体制加算3の要件にカウント
- 翌月も継続支援実施中

まとめ
外来服薬支援料1は、地域支援体制加算の実績要件にもなる重要な加算でありながら、現場では算定漏れや記録不備が目立つ項目です。
しかし、患者の服薬管理を支援するという薬剤師本来の役割に直結する加算であり、きちんとしたルールに則って対応すれば、業務の質を高めながら収益にもつながる非常に有益な制度です。
✔ 効率よく算定するためのポイントまとめ
- 対象患者のリストアップ:多剤、高齢、認知機能低下、服薬ミスが多い患者を優先
- 支援内容のテンプレート化:服薬カレンダーや整理サポートなど
- 医師との連携:事前了承または事後報告の運用体制を構築
- 薬歴記録を徹底:理由・方法・結果・連携内容を明確に記載
- 再分包は調剤行為として扱い、支援目的での整理を優先
✔ 算定できる・できないケースの境界線
- ❌ 副作用などで医師から中止指示 → 再分包のみ実施 → 算定不可
- ✅ 新処方薬とともに整理目的で再構成・連携 → 算定可能

おさらいクイズ
下記の質問に答えてから、アコーディオンを開いて解答と解説を確認してみよう!
Q1. 外来服薬支援料1を算定できるのは、処方箋がある場合に限られる?
- A. はい、処方箋がないと算定できない
- B. いいえ、処方箋がなくても算定できる
正解:B. いいえ、処方箋がなくても算定できる
外来服薬支援料1は、処方箋がなくても「服薬支援が必要な外来患者」であれば対象になります。施設患者や在宅患者には算定不可ですが、通院患者の服薬支援であれば算定できます。
Q2. 一包化後にA薬を中止し、A薬を抜いて再分包しただけのケースでは、外来服薬支援料1は算定できる?
- A. はい、整理も支援だから算定可能
- B. いいえ、調剤行為として扱われるため算定不可
正解:B. いいえ、調剤行為として扱われるため算定不可
厚労省の疑義解釈で「副作用などにより薬を中止し、再分包しただけの行為」は服薬支援とは認められないと明示されています。この場合、外来服薬支援料1ではなく再調剤料や一包化加算等での対応が必要です。
第3問:43日処方で一包化加算を算定すると点数は?
- A. 170点
- B. 204点
- C. 240点
正解:C
解説:43日以上の一包化加算は「240点」で、支援料1(185点)より高くなります。
よくある質問
Q. 外来服薬支援料1はどんな患者が対象になりますか?
服薬管理が困難な外来患者(処方箋の有無は問わず)が対象です。具体的には、多剤併用、認知機能低下、残薬常習、服薬アドヒアランス不良などが判断基準となります。
Q. 医師への報告は事前でないとダメですか?
いいえ。事前の「了解」または事後の「報告」どちらでも構いません。ただし、必ず支援内容と報告の記録を薬歴に残してください。
Q. 再分包した場合は外来服薬支援料1は算定できますか?
原則として再分包のみの対応は算定不可です(厚労省疑義解釈)。ただし、新たな処方薬を含めて服薬整理や支援を行い、医師と連携した場合は例外的に算定可能なケースがあります。
Q. 地域支援体制加算のためには何件必要ですか?
地域支援体制加算3では外来服薬支援料1または2を年12回以上算定が必要(処方箋1万枚あたり)です。加算4ではさらに厳しい要件(8項目以上)となります。
Q. 支援料1と2は同じ月に併算定できますか?
できません。同一患者に同一月での併算定は禁止されています。どちらか一方を選び、薬歴にその理由を明確に記録しましょう。
参考文献
- 令和6年度診療報酬改定 調剤点数表関連通知
- 令和6年度調剤報酬に関する疑義解釈(Q&A)
- くろやく | 外来服薬支援料1の算定要件と実践
- CLIUS MAGAZINE | 外来服薬支援の最新解説
- m3薬剤師 | 外来服薬支援料の運用とポイント
- 薬読み | 地域支援体制加算と支援料の関係








\忙しい薬剤師でもOK!最短で合格を目指すならココ/
【呼吸療養認定士】吸入指導のエキスパートへ!
「吸入薬、うまく使えてないな…」という患者さん、多くないですか?
この資格があれば、吸入デバイス指導から生活指導まで、医師に一目置かれる存在に。
✅ 呼吸器疾患への薬物療法が体系的に理解できる
✅ COPDや喘息の服薬アドヒアランスに貢献
✅ 地域包括ケアでの活躍チャンス拡大!
【透析技術認定士】電解質・水分管理の知識が武器になる!
透析患者の処方、なんとなくで扱っていませんか?
この資格で「透析処方が読める薬剤師」になれます。
✅ 血液・腹膜透析の薬学的視点がしっかり学べる
✅ 高カリウム血症やP管理などのアセスメント力がアップ
✅ チーム医療の中で活躍の場が広がる!
【認知症ケア認定士】「ただの服薬指導」からの脱却!
認知症の方との会話に困ること、ありませんか?
この資格で「認知症に寄り添える薬剤師」になれます。
✅ BPSD(行動心理症状)への対応知識も学べる
✅ 在宅・施設での多職種連携がスムーズに
✅ ケアマネや家族からの信頼も高まる!
【糖尿病療養認定士】薬だけじゃない、生活まで支える力!
HbA1cばかり見ていませんか?
この資格があれば、「生活までアドバイスできる薬剤師」に。
✅ 食事・運動・インスリンまで包括的に学べる
✅ SMBG・インスリン注射の技術支援にも対応
✅ 外来・薬局・在宅、どの現場でも活躍できる!
悩んでいる時間がもったいない。今日から一歩踏み出そう!









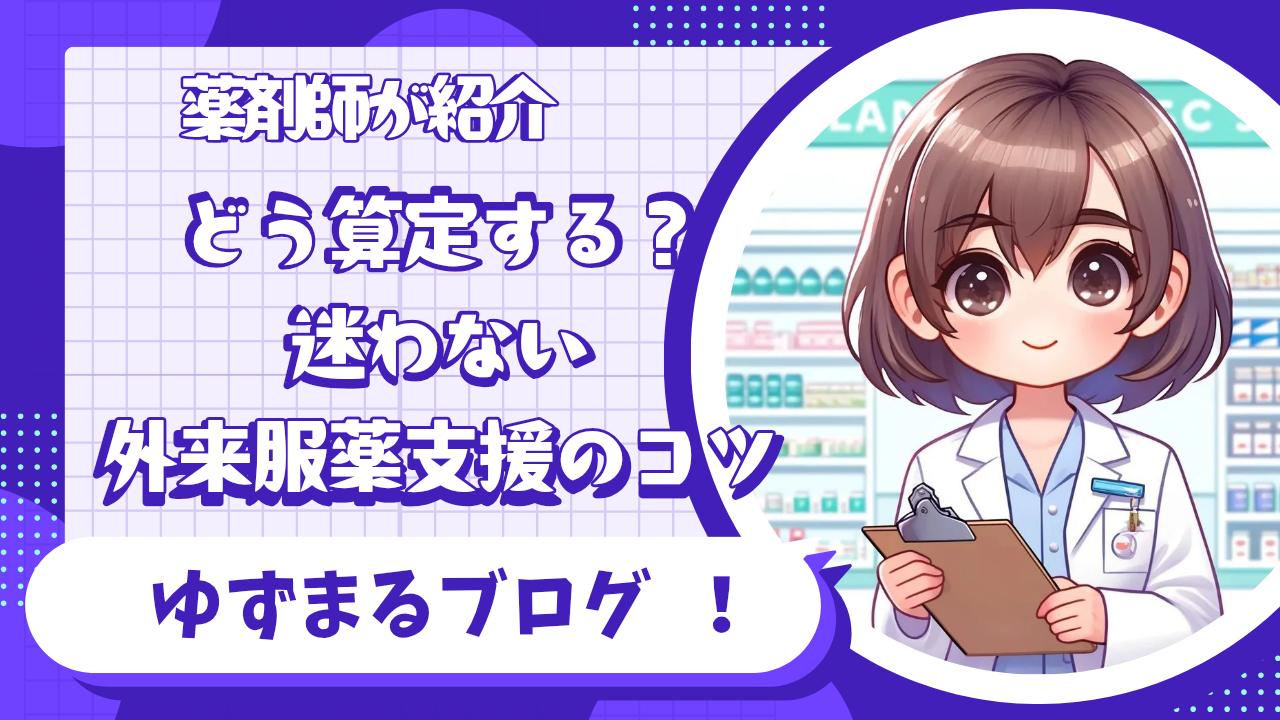

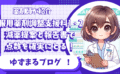
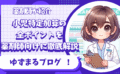
コメント